D130開発時:Hi-Fi初期のマイルストーン
SP盤の復刻盤というと針音がバチバチ鳴るのを嫌って、高域をフィルターで斬ったボンヤリした音と思うだろうが、実際は戦前でもラジオで流行した生中継ライブコンサートでHi-Fi再生が存在していた。ランシングのアイコニック・モニターは、まず放送業界の研究施設に導入された。その名残というべきか、21世紀に入って1930~40年代のSP盤による良質なリマスター盤が手に入るようになったのは喜ばしい限りだ。リリースがCDであるため、見逃しているベテランユーザーも多いだろうが、食わず嫌いはもったいない。 |
 |
シナトラ・ウィズ・ドーシー/初期ヒットソング集(1940~42)
「マイウェイおじさん」として壮年期にポップス・スタンダードの代名詞となったフランク・シナトラが、若かりし頃にトミー・ドーシー楽団と共演した戦中かのSP盤を集成したもので、RCAがソニー(旧コロンビア)と同じ釜の飯を喰うようになってシナジー効果のでた復刻品質を誇る。娘のナンシー・シナトラが序文を寄せているように、特別なエフェクトやオーバーダブを施さず「まるでライブ演奏を聴くように」当時鳴っていた音そのままに復活したと大絶賛である。有名な歌手だけに状態の良いオリジナルSP盤を集めるなど個人ではほぼ不可能だが、こうして満を持して世に出たのは食わず嫌いも良いところだろう。しかしシナトラの何でもない歌い出しでも放つ色気のすごさは、女学生のアイドルという異名をもった若いこの時期だけのものである。個人的には1980年代のデヴィッド・ボウイに似ていなくもないと思うが、時代の差があっても変わらぬ男の色香を存分に放つ。 |
 |
ジャイヴをもっとシリたいか?/キャブ・キャロウェイ(1940~47)
(Are you HEP to the JIVE?)
映画「ブルース・ブラザーズ」で健在ぶりをみせたキャブ・キャロウェイをどういうジャンルに含めればいいかを正確に言い当てることは難しいだろう。ジャズだというとエリントン楽団をコットン・クラブから追い出したと疎まれるし、R&Bというにはビッグバンド中心で大げさすぎる、Hip-Hopのルーツといえば内容が軽すぎる、いわゆるジャンピング・ブルースというジャンルも他に例が少ないので、そういう言い回しがあったんだと思うくらい。でもそんな検証は実に無駄だし、ラジオから流れる陽気な調べは、放送禁止用語を軽々と飛び越えキャロウェイが連発する黒人スラング辞典まで生まれるような現象まで生み出した。そういう俗っぽさからブルースが心を鷲掴みにするまでそれほど時間はかからなかっただろう。 |
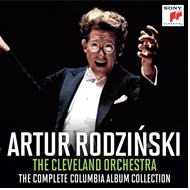 |
ロジンスキ/クリーヴランド管 コロンビア録音集(1939-42)
LP規格の開発元だった米コロンビアだが、最初のLPはテープによるHi-Fi録音ではなく、SP盤のために製作された録音をLP盤にしたものだった。コロンビアレコードがソニー傘下にはいって、一番幸福だと思えるのが古い録音のデジタル・アーカイヴである。詳細は分からないが金属原盤から復刻したと思わしき鮮明な音で、本当に1940年代初頭の録音なのかと思うほどである。しかしLPでもあまり出回らなかったマイナーなアーチストを丁寧に掘り起こし、文字だけなら数行で終わるようなクリーヴランド管の原点ともいうべき事件に出会ったかのような驚きがある。録音として最も良いのはシェヘラザードだが、個人的に目当てだったのは初演者クラスナーとのベルクVn協奏曲で、英BBCでのウェーベルンとの共演では判りづらかったディテールが、最良のかたちで蘇ったというべきだ。 |
 |
美空ひばり 船村徹の世界を唄う1(1956~64)
初期のものはSP盤でのリリースだが、大事にテープを保存していたのだと感心するし、なによりも二十歳前後の美空ひばりの若い色香の漂う声が新鮮である。マドロス歌謡が中心なのだが、おそらく帰還兵との関係もあって、この主題が頻繁に取り上げられたのだろうが、なんとなくハワイ、ブラジル移民とも重なり、裏声を多用したハワイアンの影響ともとれるのだ。この裏声を自由に操る七色の声が、美空ひばりの真骨頂ともなった。これはその修行時代から「哀愁波止場」での完成にいたるまでの記録でもある。途中の1959年に東京タワーをあしらった歌が入るが、これが第10回コロムビア全国歌謡コンクールの課題曲。このコンクールは過去に、コロンビア・ローズ、島倉千代子などを輩出してる。 |
 |
ブルービート/スカの誕生(1959-60)
大英帝国から独立直前のジャマイカで流行ったスカの専門レーベル、ブルービート・レコードの初期シングルの復刻盤である。実はモッズ達の間では、このスカのレコードが一番ナウいもので、ピーター・バラカン氏が隣のきれいなお姉さんがスカのレコードをよく聞いていたことを懐述している。ノッティングヒルに多かったジャマイカ移民は、このレーベルと同時期からカーニバルを始めたのだが、ジャマイカ人をねらった人種暴動があったりして、1968年に至るまで公式の行事としては認可されない状態が続いていた。それまでのイギリスにおけるラヴ&ピースの思想は、個人的にはジャマイカ人から学んだのではないかと思える。ともかくリズムのノリが全てだが、それが単調に聞こえたときは、自分のオーディオ装置がどこか間違っていると考えなければならない。 |
様々な音楽ジャンルに挑んだ1960年代
1960年代というとロックを代表するカウンターカルチャーに話題が傾きがちだが、ステレオ盤の販路が広がるにしたがいエコーに包まれたお花畑サウンドが増えていった。実際にはPAシステムのほとんどは旧規格のものが使われており、レコードで聴いたほうが音質が良いという定説もよく聞かれた。このためこの時代の熱情を肌で感じるオーディオは、一昔前のものを希求することになるが、D130は次の1970年代に花咲いたように、その血筋を備えていたのである。 |
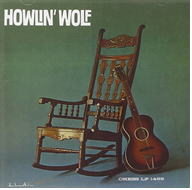 |
ハウリン・ウルフ(1962)
モダン・ブルースで異彩を放つチェス・レコードでのデビュー盤で、枯れ切ったダミ声で歌うブルースは、まさにシカゴの喧騒をつんざくように響く。この荒れた感じを包み隠さずに表現しうるのが、D130のようなヴィンテージJBLの本来の味わいである。いや味わいというような呑気なものではなく、噛みつかれそうな勢いで声が迫ってくるというほうが正しいだろう。これがオーディオ的に優秀録音である理由はJBLだけが知っているといえる。 |
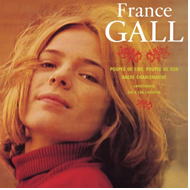 |
フランス・ギャル(1964)
男気に溢れるJBLの好きな人には、やや意に沿わないかもしれないが、フランスのイエイエというダンス・チューンは、もともとゴーゴーの意味で、言わずもがなJBLはディスコにも強い相性を示すわけで、これを見逃すわけにはいかない。
このフランス・ギャルのデビュー盤も、ユーロビジョンで優勝した凱旋録音で、やや舌足らずな少女の面影を残す歌い口は、フレンチ・ポップスの定番となったばかりか、日本のアイドル路線のお手本ともなった。一方で、ちゃんとしたモノラル・スピーカーで聴いたことのない人にとっては、ただの太鼓持ちにみえるバックバンドのキレキレの演奏に気付きにくいことだろう。大所帯に見えながら奥の奥まで澄み切ったリズム運びは、このアルバムのピュアな感覚をいつまでも保っているのだ。 |
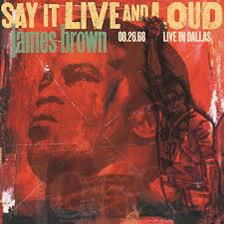 |
ジェームズ・ブラウン/SAY IT LIVE & LOUD(1968)
録音されて半世紀後になってリリースされたダラスでのライブで、まだケネディ大統領とキング牧師の暗殺の記憶も生々しいなかで、観衆に「黒いのを誇れ」と叫ばせるのは凄い力だと思う。ともかく1960年代で最大のエンターテイナーと言われたのがジェームズ・ブラウン当人である。そのステージの凄さは全く敬服するほかない。単なるボーカリストというよりは、バンドを盛り上げる仕切り方ひとつからして恐ろしい統率力で、あまりに厳しかったので賃金面での不満を切っ掛けにメンバーがストライキをおこし、逆ギレしたJBが全員クビにして振り出しに戻したという伝説のバンドでもある。長らくリリースされなかった理由は、おそらくこの時期のパフォーマンスが頂点だったということを、周囲からアレコレ詮索されたくなかったからかもしれない。ステージ中頃でのダブル・ドラムとベースのファンキーな殴打はまさしくベストパフォーマンスに数えられるだろう。 |
 |
フィルモア・イーストの奇蹟/アル・クーパー&マイク・ブルームフィールド(1968)
ロックのライブ録音というと、ややアクシデント的な話題が先行して、なかなか演奏の中身まで行き着かない。それも一期一会のステージパフォーマンスとなれば、なおの事である。この録音は、そうした奇遇が重なって成り立っている1960年代終盤の記録である。
ブルース・ギターの名手マイク・ブルームフィールドとキーボディストのアル・クーパーは、ボブ・ディランのハイウェイ61で共演して以来の仲良しで、結局ディランがザ・バンドに切り替えた後に、「スーパー・セッション」と題したインスト中心の即興演奏ステージを展開していた。基本的にブルース・ロックの古典ともいえるような構成なので、オリジナル曲を掲げたクリームや派出なパフォーマンスのジミヘンのような脚光は浴びなかったし、同じメンツでも当時としては西部での公演がリリースされたので、こちらは2009年になって発売された発掘音源である。
この録音で何をチェックしているかというと、冒頭のアル・クーパーのMC部分で、胸声が被らずにクリアにしゃべれているか、それでいてインスト部分がスカキンにならず、ブルースのこってりしたタメが出きっているか、など色々とある。 |
1970~1980年代の異形のポップスター
ここではエンタメの王道を行くのを一端逸れて、二度と現れない個性あふれるタレントを拾い上げてみた。こうした演奏は、ちょっとした機敏に触れるとリアリティが増すが、D130は見掛け倒しの分解能などお構いなしに、楽音を前に前に進ませていく。そうしたボディごと体当たりしてくるフィジカルな体感は、Hi-Fiの創成期から大事にされてきたものである。 |
 |
乙女の儚夢(ロマン)/あがた森魚(1972)
四畳半フォークもここまで化けると、むしろアッパレというほかない。冒頭から白昼夢にうなされたオヤジが、猫なで声で大正時代の女子高生への憧れと昭和の零落する品性を歌うなんて、高音質という役割がほとんど意味をなしていないことは一目瞭然。林静一氏のマンガに影響を受けたというが、全然上品にならないエロチシズムは、どちらかというと、つげ義春氏のほうが近いのではないか。音楽的にはフォークというよりは、アングラ劇団のサントラのようでもあるし、かといって明確なシナリオがあるわけでもない。しかし、結果として1970年代の日本で孤高のコンセプトアルバムになっているのだから、全く恐れ入るばかりである。 |
 |
ジュディ・シル:BBC Recordings(1972-73)
コカイン中毒で亡くなったという異形のゴスペルシンガー、ジュディ・シルの弾き語りスタジオライブ。イギリスに移住した時期のもので、時折ダジャレを噛ますのだが聞きに来た観衆の反応がイマイチで、それだけに歌に込めた感情移入が半端でない。正規アルバムがオケをバックに厚化粧な造りなのに対し、こちらはシンプルな弾き語りで、むしろシルの繊細な声使いがクローズアップされ、それだけで完成された世界を感じさせる。当時のイギリスは、ハード・ロック、サイケ、プログレなど新しい楽曲が次々に出たが、そういうものに疲れた人々を癒す方向も模索されていた。21世紀に入って、その良さが再認識されたと言っていいだろう。
カントリー・ブルースのヨーデル節を独自に発展させた歌い口もかなり個性的だが、聴きどころは、ブルース感あふれたピアノの弾きっぷりである。実は伴奏者としても一流だったが、それを自分の信じる歌のためだけに使っている贅沢さが、ラジオ局の一角で行われたライブ中継を特別な空気で満たしている。 |
 |
放射能/クラフトワーク(1975)
舞台で四角いシンセサイザーの前にロボットとなって立つネクタイ姿の男たち、という特異なパフォーマンスで一世を風靡した電子音楽のパイオニアのような存在だが、日本では必ずしも熱狂的に迎えられたわけではなかったように思う。というのも、ユリゲラーやブルースリーに熱狂していた当時の日本において、感情を殺したテクノポップスは夢物語では片づけられない、四角い満員電車で追体験するただの正夢だったのだと思う。標題のRadio-Activityというのは、古いドイツ製真空管ラジオを模したジャケデザインにもあるように、レトロなテクノロジーと化したラジオ放送を活性化する物質とも解せるが、原子力が一種の錬金術として機能した時代が過ぎ去りつつある現在において、二重の意味でレトロフューチャー化している状況をどう読み取るか、その表裏の意味の薄い境目にディスクが埋まっているようにみえる。例えば、放射能と電子を掛け合わせたものは原子力発電による核の平和利用なのだが、そのエレクトリック技術に全面的に依存した音楽を進行させたのち、終曲のOHM
Sweet OHM(埴生の宿のパロディ)に辿り着いたとき、電子データ化された人間の魂の浄化を語っているようにも見えるが、楽観的なテーマ設定が何とも不気味でもあるのだ。おそらくナチスが政治的利用のためにドイツ国民の全世帯に配った国民ラジオのデザインと符合するだろう。よくコンピューター音楽と間違われるが、純然たるアナログシンセによるパフォーマンスで、この音色がなかなか再現しにくい厄介者であるが、ひとたびコツを掴むと固有のビビッドな感覚がよみがえってくる。 |
 |
ヴィソーツキイ:大地の歌(1977)
酒の飲みすぎで潰したようなダミ声で機関銃のように言葉をがなりたてる旧ソ連の国民的シンガーソングライター。日本ではウィスキーのCMにも起用されたが、それ以前はほとんど知られることがなかった。共産主義国でのブルースということ自体がマイナーなうえ、政府批判とも取れる歌詞のゆえ当然のように発禁となったが、市民はこっそりカセットにコピーして聴いていたという。この録音はフランスでのセッションだが、実質的に残された最良の録音ということになろう。 |
 |
沢田研二「A面コレクション」(1971~86)
ソロ活動開始の1970年代からヒットメーカーだった1980年代のポリドール時代のシングル盤を集めたベスト盤だが、ここでは2~3枚目の「勝手にしやがれ」から「AMAPOLA」が1980年前後に注目しよう。ジュリーの声は低い声でもセクシーなハイトーンの艶が載る七色系の声色の持ち主だが、そこにロック魂を注ぐべく専属バンドを定めてキッチリとレコーディングをする人でもあった。
歌番組では、アイドル全盛期を横目で睨みつけたファッション・リーダーとしても才能をみせたジュリーだが、当時アラサーだったのに今でいうアラフォーの色気たっぷりの魅力で押していたことが判る。そのダンディさからデヴィッド・ボウイに喩えるアジアのファン層もいるようだが、むしろプロモーション方法はマイケル・ジャクソンと同じベガス風のものだった。そのデジャヴなレトロ感を生かした味わいが、D130なら引き出せるのだ。 |
 |
矢野顕子:ただいま(1981)
もともと即興的なピアノの名手で4人目のYMOのように参加していた頃、硬派なテクノを子供も楽しめるポップスの本流に読み直した点で今でも十分に新鮮な味わいをもつ。最初のアルバム「ジャパニーズ・ガール」から独自の世界観をもっていたが、前作がフルパワーでテクノポップにフィジカルにぶつかった力作だったのに対し、半年後に出したこのアルバムは何か置き忘れてきた記憶の断片を掻き集めた感じで、むしろアットホームな彼女の魅力が引き出されている。ともかく にゃんにゃん わんわん で音楽ができてしまうのだから、もはや怖いものなしである。実験的な無調音楽も含まれており、CMヒット曲「春先小紅」を期待して買った人は、いつ聞けるのかとドギマギして聴いていたかもしれない。 |
 |
フューチャー・ショック/ハービー・ハンコック(1983)
意外に思うかもしれないが、本作のような電子音楽とD130の相性は結構キマッテいる。それもそのはずで、そもそも電子楽器はエレキギターやハモンドオルガンのようなものから始まり、その血脈のなかにD130も加わってきた歴史があるからだ。それと本作がヒップホップのテイストを取り入れたと言いながら、大衆に受け容れられやすいダンサブルな要素が満載だからこそヒットしたということも、1970年代のディスコブームに乗っかったJBLの得意分野なのだ。そこがこの曖昧なカテゴライズのなかでフワフワしている、このアルバムの立ち位置を明らかにしていると言えよう。 |
無国籍な放浪を続ける21世紀のポップス
ヴィンテージJBLといえば、昔ながらのモダンジャズが筆頭に上がり、さらにロックでも1960年代後半から1980年代前半の、ややレガシーに浸り気味なところがあるが、けして新しい録音と相性が悪いわけではない。むしろフィジカルな肉感をもつミュージシャンの実体感を再現してくれる、リプロデューサーとしての本質を外さない造りの良さが際立ってくる。 |
 |
スタンダーズ/トータス(2001)
シカゴ音響派と言われた1990年代アメリカのインスト音楽のひとこま。とはいえ、今どきだと全て打ち込みでもっと複雑なものをやってしまいそうなところだが、そこは生演奏可能なフィジカルな範囲で留まりつつ、クールな情念を注ぎ込むよう心を配っている。ここでのスタンダード=ポップスの定義は、ジョージ・シーガルの彫像作品をポップアートと呼ぶくらい意味のないもののように感じる。トータスを知ったのはベスト・ヒット・USAで、小林克也さんがクールなMTVの新しい潮流のようなことで紹介していた。MTVも成熟してテレビ用プロモーションの焼き直しになりつつあった時代に、何かしらアートなものを捜した結果だろうが、こんなこと覚えている自分も何なんだろうと思う。 |
 |
MAISON MARAVILHA/ジョー・バルビエリ(2008)
国内レコード会社のオーマガトキというレーベルのリリースするアルバムは、マニアックなものが多いように思うが、コアな音楽ファンを焚きつけてやまない。個人的には旧ソ連のダミ声シンガーのウラディミール・ヴィソツキーの1970年代フランス吹き込み盤で知ったのだが、イタリアの遅咲き男性シンガー・ソングライターの本アルバムも気付いてみればオーマガトキ。ボサノヴァとイタリア映画を組み合わせたような不思議な語り口は、上質なカフェ音楽でもある。どこかで聴き覚えあると思うと、あがた森魚「乙女の儚夢(ろまん)」と似ていなくもない。男のセンチメンタルといえば、行き場もない路地裏で犬も喰わぬ悶々とした感じだが、変態を略してエッチというなら、両者は人間の声のひとつの魅力というべきだろうか。あらためて聞き比べると、どちらも何でも鑑定団で本人評価額を大きく超えたプレミアムな判定と相成るわけだ。男のセンチメンタルはけして安くはないのだ。 |
 |
ガイガーカウンターカルチャー/ アーバンギャルド(2012)
時代は世紀末である。ノストラダムスの大予言も何もないまま10年経っちゃったし、その後どうしろということもなく前世紀的な価値観が市場を独占。夢を売るエンタメ商売も楽ではない。
この手のアーチストでライバルはアイドルと正直に言える人も希少なのだが、別のアングラな部分は東京事変のような巨大な重圧に負けないアイデンティティの形成が大きな課題として残っている。その板挟みのなかで吐き出された言葉はほぼ全てがテンプレート。それで前世紀にお別れを告げようと言うのだから実にアッパレである。2人のボーカルに注目しがちだが、楽曲アレンジの手堅さがテンプレ感を一層磨きを上げている。
それと相反する言葉の並び替えで、敵対するステークホルダー(利害関係者)を同じ部屋のなかに閉じ込めて、一緒に食事でもするように仕向けるイタズラな仕掛けがほぼ全編を覆ってることも特徴でもある。それがネット社会という狭隘な噂話で作り出された世界観と向き合って、嘘も本当もあなた次第という責任を正しく主張するように筋を通している。個人的には情報設計の鏡というべき内容だと思っている。
それからさらに10年後、2020東京オリンピックで空中分解した1990年代のサブカル・ヒーローとヒロインの宴を肴にして聴くと、役所もテンプレという壮大なフィクション国造りの構造が見えてくる。キスマークのキノコ雲で街を満たせたら、という願いは決して古びることはないと思う。 |
 |
Frozen Silence/マチェイ・オバラ・クインテット(2023)
ポーランドのサックス奏者マチェイ・オバラのリーダー作だが、マチェイ自身は新型コロナのパンデミックでポーランドでの活動が完全に停止し、さらに海外ツアーの道も閉ざされたとき、ワルシャワを離れて一人森のなかを放浪しながら楽曲の素案を練っていたという。ようやく2022年夏にノルウェーのオスロで吹き込むことができたのだが、その溜まっていた情念を吐き出すかのように、無調のように半音階で彷徨う音楽は、行く当てのない道を2回の冬を越しながら過ごすことの恐怖と背中合わせだったことが判る。ジャズというよりは、ロードムービーの即興のエピソードを観ているような、別の意味での臨場感が漂うアルバムになっている。 |

