

我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。「PIEGA現わる!」は、これまでピュア・オーディオなるものには、むしろ反対の立場を取っていた筆者の改心ともいうべき出来事が切々と綴られています。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)なぜかJBL+AltecのPA用スピーカーをモノラルで組んで悦には入ってます。 5)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIEGA現わる!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【購入理由】 購入の動機はいたって単純だった。現在のニアフィールド・スピーカー+スタンドというのが、赤ちゃんがハイハイするのに不安定で危険だという妻の進言だった。これに対する私の反応はいうまでもない。新スピーカー購入の天からの声だと信じたのである。次の週末にはひとり秋葉を徘徊していた私が居た。  赤ちゃんが動き回れば危険と感じられるトップヘビーな外観  購入の原因となった天使(笑) ページ最初へ 【候補となった機種】 候補の前提となったのは以下のとおりだった。 1.トールボーイもしくはスタンド一体型 2.予算はペア50万前後 3.スタイルの良いこと この頃、ヨーロピアン・ジャズなどをオサレに聴きたいなんて妄想が強かったせいか、デザインから入るというのが今回のコンセプトになった。この基準で考えたのが以下の機種。富士通テン以来、何となく奇抜なデザインが好きなのだ。
ページ最初へ 【試聴結果】 秋葉広しといえどこれら全てを置いてある店などない。3軒をはしごすることとなった。SolidAcousticsはトモカ電気、PIEGA TWENと富士通テンTD712zはダイナミック5555、PIEGAのTWENとTC50の比較がサウンドクリエイトだった。 最初のトモカ電気は設備PA用という説明を続けていたが、実際の音も中規模のホールで鳴らしてちょうど良い感じで妙に納得した。呼吸球はさすがにスウィートスポットが広いけど、昔のBOSEのような大まかな鳴り方であまり釈然としない。ダイナミック5555は客足が激しいのであまりゆっくり試聴できないのと、爆音で鳴らしてどうだ!と言わんばかりのアプローチで自分には門外漢。こういうのは大体、人の話もゆっくり聞いてもらえる場所が良い。電話での煩雑な問い合わせで店員が対応できないのと、試聴する前を悠然とウロウロする客の多いこと。そういう意味でサウンドクリエイトは良い時間を過ごさせてもらったように思う。試聴時間の予約を取って置いたのも良かった。試聴中に輸入代理店のヒューレンの人も来たりして、終止和やかな感じで終わった。 TC50とTWENの聴き比べは、TC50がフロア型のゆったりした鳴り方なら、TWENは全くのニアフィールドの鳴り方。背丈、横幅は同じなのに、全く違う音場なのに驚いた。そして気付いたのが、今の自分のスタイルが意外に緊張感の高い音だったということ。もうひとつは、TC50の中域は抜けだしが明瞭で、高域のリボンでトーンを決まらないようにマイルドに仕上がっていること。ボーカルが繊細なだけに留まらず、体温が感じられる厚みもあったのはとても好感が持てた。他で試聴したTWENとTD712zは共に高域上がりのトーンで、ニアフィールドのスタイルに押し留まる感じだった。TC50のアルミ押出し成型の台形箱は、ユニット固定のアースもしっかりしていてベースのタイトさも良好。この点は富士通テンの構造的特徴を知って以来、外せない要点のひとつだ。何と言ってもアルミ押出し材のシームレスな造形美を堪能できるのがワンランク違うなにかを感じさせる。 結局、試聴して決めたのは、何の脈略もなく聴いてみたPIEGA TC50でした。  PIEGA現る!テレビ台も変えて銀ギラギンに! ページ最初へ 【ジャンルを問わない華麗さ】 何となく気まぐれで購入したかに見えたPIEGA TC50だったが、意外なサプライズもあった。今まで散々苦労を強いられた50年代ドイツ放送録音、60年代ロック、70年代テレビまんが、などなどが驚くほど明瞭に鳴り渡るようになったのだ。
あまりキワモノばかり良いというと、PIEGAが特殊なスピーカーかと思われても困るので、普通に相性の良い録音を紹介する。清楚ななかに高いポテンシャルを秘めるのがPIEGAの特徴だ。
ページ最初へ 【音調を整える】 1950年代からのHi-Fi録音で使われたマイクは、ほぼ例外なくノイマン社の大型ダイヤフラムのコンデンサー・マイクが用いられていました(A図)。このマイクはほぼフラットな特性のなかに中高域に幾分の輝きのあるキャラクターをもたせてありますが、これは精度の良い金属箔を用いたダイヤフラムを2way化することによって高域を持ち上げているからで、深く伸びた低音と明瞭な高域が得られ、大型ダイヤフラムだけがもつ、2kHzにあるリッチな艶はアナログテイストの代名詞として今も愛されています。一方で、低域の回り込みによるブーミーな膨れあがりや、中高域でのカサカサした音などを過敏に拾う癖もありました。 こうしたノイマン型マイクの特性を考慮してニュートラルな音調に整えるには、以下の方法が有効です。ひとつは実際の収録音圧と再生音圧の差分を補うためにラウドネス補正を掛けること、ふたつめはコンデンサー・マイクの近接効果(中低音が膨れあがる現象)をキャンセルして音調をスマートに収めることです。これらを補正して聴感上フラットにしたのがB図です。(このことに関する仔細なデータはAES研究部会のBruce Bartlett氏の論文参照) B図から判ることは、一般にフラットなままの特性ではプレゼンスが強すぎて中高域がうるさく、逆に8kHz以上のアンビエンス成分が薄く感じられ音がくぐもることが判ります。 ちなみにラウドネス補正のみのC図の特性は、1950年代の英米で流行ったもので、ビンテージ・スピーカーにはお馴染みのものです。音離れが良いことで知られるものですが、録音はフラットに録られることで実力を発揮します。
ノイマン社はドイツの老舗ですが、PIEGA社のあるスイスのチューリッヒはドイツ語圏で、ここら辺のサウンド志向も似ているのかもしれません。リボン・ツイーターの抜けの良さと、コーン・ウーハーの暖かみのある音調は確かに似ています。パンチングメタルのグリッドを備えたPIEGAの見栄えは、何となくコンデンサーマイクを拡大したかのような感じに見えてきます。ふたつはバウハウスに始まるモダンデザインに通底する同じデザインの伝統に立ったものといえます。 ドイツ的な音の質感で憶えていたのが、20年前にとある店で聴いたクラングフィルムのスピーカーで、大型ホーンの2wayで高域など伸びてないのに、シルキーな中域でそのまま音楽で包み込んでしまうような物腰の良さが印象的でした。そうした60年前から育まれていた技術の粋が、今のHi-Fi録音の原点というのは疑いなく、今回その伝統を再確認した次第です。 これまで不自然に感じていたノイマン社のトーンですが、ここで一気にノイマン社のドメスティックな伝統に回帰したような感じです。その意味で敵の軍門に下ったという表現が適切かもしれません。 今回のトーンは、赤ちゃんのために小音量でも聴けるものに調整してみました。B図との違いは100Hz〜900Hzを右肩上がりにしている点で、若干前のめりになる音調です。これが50年以上前の埃を被ったような録音をみるみる甦らせたのですから、まさにケガの功名というべきでしょう(懐が痛いという意味も含めて)。 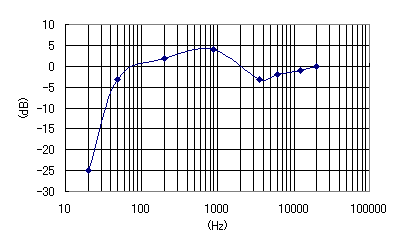 今回の音調:小音量向けに合わせたがサプライズの連続だった ページ最初へ 【ドイツ製の音響機器】 邂逅邂逅と書いて置いても何のことやら判らないので、ここでドイツ語圏でのスタジオ用音響機器を年代別にピックアップします。ドイツは音響産業の早い時期から共通規格でのシェア割りをする形態があり、最初は映画産業のKlangfilmに技術集約され、その後放送系のTelefunkenに移り、1960年代から各社が独自ブランドに戻るという感じになっています。そのため1930年代から1960年代までは、ひとつの筋の通った録音になっています。
こうして見るとHi-Fiの基本セットは1930年代には完成していたようです。当時のドイツからの放送を聴いた外国の人たちは、テープ録音を生中継と勘違いしたというのですから、ドイツの人々は無料でこうしたサービスを受けられたというわけです。そのためテレフンケン製のスピーカーは、ラジオ用は非常に多く見受けられますが、スタジオ用ともなるとたまに出物がある程度でしかも高値の華です。これはノイマン社のカートリッジと同じく、門外不出の品というべきものでしょう。1960年代以降はスイス、オーストリアの製品が優勢になってきますが、基本的なトーンには共通点があります。 ページ最初へ 【日本製でもドイツ・デザイン】 自分持ちの機器のなかにもドイツ人デザイナーのものがありました。CECにはカルロス・カンダイアス氏というスペイン〜ポルトガル系のドイツ人が居て、スマートでリーズナブルなオーディオ製品を設計しています。CDトランスポートのTL51Zを設計したのも彼です。多くの日本製と同じ角張ったデザインだが、あらためて見るとドイツ・デザインの系統を受け継いでいます。付属のように買ったDAコンバーターのDX51もデジタル信号をAES/EBU出力で繋ぐとシルキーで安定した音になり、意外に買い換える気が起こらない不思議な製品なのです。全体に低域モリモリという音ではなく、少し足らないというくらいにスマートに収めています。この辺はオペアンプの音をそのまま出力している感じで、基本的な音の鮮度を優先しているように思います。  ベルトドライブのターンテーブル方式(TL51X) 日本とドイツ・モダン・デザインの付き合いは意外に古く、バウハウスに学んだ山脇巌、道子夫妻によって1930年代に紹介されて以来の伝統があります。モダニズムそのものは何となく高度成長期の功利主義に飲み尽くされた感はあるが、日本のモダン・デザインを見直すきっかけになると良いように感じています。 ページ最初へ 【スイス製の血筋】 スイス製の音響機器で忘れてはならないのが、NAGRA社のポータブル・テープレコーダーで、正確さと堅牢さを兼ね備えた名器でした。特に野外ロケには欠かせない一品で、多くの歴史的瞬間を捕えてきました。小型であるにも関わらず、テープ速度の安定性も良かったので、テレビでのインタビューの編集など、フィルムとのシンクロにも十分に耐えられる品質をもっています。  歴史的名器 NAGRA III スイス製のレコーダーの老舗にはSTUDER社がありますが、STUDERが少し艶やかなビーナスのような存在なら、NAGRAは知的なミネルバのような感じです。STUDER社がNeumann社やShoeps社のマイク、AKGのヘッドホンという流れなら、NAGRA社はSENNHEISER社のマイク、BeyerDynamics社のヘッドホンというように、同じ独墺系でも生真面目な感じの機器を選ぶ傾向があります。(面白いことにSENNHEISER社のヘッドホンは艶やか、BeyerDynamics社のマイクは暖色系と、同じ会社でも違った傾向をもっています。)かといってNAGRAの音がカチカチのソリッドというわけでもありません。あえていえば機材という存在を無くした、空気のような存在というべきでしょうか。その辺がスイスの職人的な一面を浮び上がらせています。
実のところ、PIEGA社も当初は前者をターゲットに置いていたような感じがします。いわば洗練されたスイス・オーディオの一翼を担う感じです。しかし最近の傾向はもう少し融通が利くような感じで、いわば誰にでも受け容れられるユニバーサル志向に転じているように思います。 この辺は好みの分かれるところですが、オーディオの歴史との相関に考えさせられるところ十分です。個人的には無個性という個性に投じた結果、山のように積み上がるCDを新鮮な気持ちで楽しむことができるので良かった、とだけ伝えましょう。 ページ最初へ |