| ①ラジオ放送音源 |
|
 |
Live at the BBC(1962~65)
ザ・ビートルズ
BBCでのみ使われたColes 4048というリボンマイクで、しかも宙づりのオフマイクで録られた番組収録は、EMI正規録音に比べるとカビくさいモゴモゴした音で、軽トラックでAMラジオを聞くようなノスタルジックな録音。いくらコレクターズ・アイテムとはいえ、普通の人ならガッカリである。
ところがロクハンから聞こえるのは、放送局近くで安定してエアチェックできたような音。つまり、ビートルズが局に来ていて、スタジオ・ライブをやってます。だいたいそんな感じ。これを、ながらで聞き流す。なんと贅沢な時間なのだろう。ロカビリー中心でカバー曲を演奏するサービス精神旺盛な頃の若きビートルズ。ロックをイギリスのお茶の間に紹介したパフォーマンス・バンドでもあった。
|
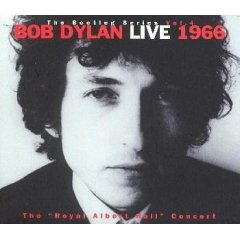 |
ロイヤル・アルバート・ホール・ライブ(1966年)
ボブ・ディラン&ザ・バンド
この歴史的なコンサートも、当時の録音技術というか、現地での録音クルーの錯綜ぶりが災いして、前半のNAGRA製レコーダーのアコースティック・ステージはまだしも、後半のAmpex製マルチレコーダーでのエレクトリック・ステージはリミッター掛かり離しの潰れた音響で霹靂する。世に言う悪音ライブの典型である。
これを斜め横からモノラルで聞き流す。録音のアラは全く消えて、音楽だけが聞こえてくる。そして、辛辣な言葉で客をあおるトークも音楽と同様に自然に聞き取れる。まさにドキュメンタリー番組そのものである。
|
 |
Cream BBC Sessions(1966~68年)
クリーム
上記のディランの嵐が去って残したもの。それは新しいヘヴィ・メタルというジャンルの誕生である。それもあのイギリスで。BBCでのセッション録音は、まだアイディア段階の未発表曲も含む、実験的な要素が多いもので、ギター、ベース、ドラムの3人がガッチリ組んで繰り出すサウンドは、エフェクターを噛ませずに乾いた生音をそのまま収録している。このため、普通のステレオで聴くと、収録毎の音質の違いなどが気になり、なかなか音楽に集中できない。正規録音のあるなかで、長らくお蔵入りしていた理由もうなずける。蛇足ながら実験的というのは、セッション中の彼らのファッションがモッズ風で、サウンドの斬新さに追いついていなかったことも挙げられる。
これもモノラルで斜め横から聞き流す。するとトータルなバランスのなかで、バンドの目指すサウンドの全体像が把握できる。ともかく一発勝負の収録だったことの緊張感が先行しながらも、サウンドを手探りで紡ぎ上げていく感覚はBBCセッション独特のものだ。今の時代にこうした冒険的なセッション収録は許されないことを考え合わせると、オーディオも含めて音楽業界がビジネスにがっちり組み込まれたことの反省も感じる。
|
 |
シングス・ララバイズ・オブ・バードランド(1954年)
クリス・コナー
ラジオ風のアナウンスで始まる、いかにもそれらしく装ったアルバム。モノラルで女声ボーカルといえば、フルレンジの王道である。2ch分所有している方は、ぜひ片チャンネルのみで聴いてほしい。そのときは椅子を移動して斜め横にかまえて。元の試聴位置には、コーヒーテーブルを置けば、これまでと違うリスニング空間ができること請け合い。 |
 |
なつかしの昭和テレビ・ラジオ番組主題歌全集(1947~75年)
ラジオといえば安っぽいイメージあるが、当時の日本の放送録音は、戦後になってアメリカ製の機材が大量に入ってきた時代のもので、音のほうはとても安定して保存状態も良い。1950年代の放送アーカイブで、ここまで品質の良いものは他の国でも珍しいと思う。PE-16Mとの相性はいうまでもない。まさしく、このために作られたモニタースピーカーだからだ。音の抜けだし、レンジ感がピッタリとはまっている。 |
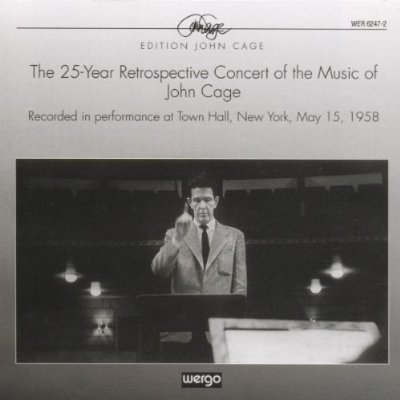 |
25-Year Retrospective Concert(1958年)
John Cage
ジョン・ケージ45歳のときにニューヨークの公会堂で開かれた、作曲活動25周年記念コンサートのライブ録音。友人で画家のジャスパー・ジョーンズ、ロバート・ラウシェンバーグらが企画したという、筋金入りのケージ作品だけのコンサートだった。さすがに4'33"は収録されいないが、前期の作品がバランスよく配置されたプログラムである。公会堂でのコンサートは夜8:40から開始されたにも関わらず、聴衆のものすごい熱気に包まれた様相が伝わり、当時の前衛芸術に対するアグレッシブな一面が伺えて興味深い。
この歴史的な録音の状態は、ぶっつけ本番のライブ収録という割には良く録れたもので、周波数レンジも今回のシステムにぴったりである。ファースト・コンストラクションIII(メタル)の鮮明な音色感はともかく、他のシステムではあまり聞く気になれない、プリペアード・ピアノのためのソナタとインターリュードでも、静謐な印象が奥深く広がってくる。
|
 |
Rock the Joint(1950年代)
ロカビリーのコンピレーション・アルバム3枚組。この時代の軽音楽はアセテート盤へのダイレクトカットが基本で、編集など全くなしの本番一発録りである。「監獄ロック」のプレスリーが新人デモのためテープ録りをしているが、当時としては破格の扱いで、多分プレスリー級のドル箱歌手が一般に使っている機材を集めたものと思う。素材はテープダビングか、ドーナッツ盤の復刻だが、これは後者のような感じがする。前から不思議に思っていたのは、RCA等の正規CDはイコライザーが強すぎてギンギンに鳴り、復刻組はモコモコしたレンジの狭いことでレトロな雰囲気を出した感じ。そんなトラウマだらけのサウンドを積極的に集めようとは思っていなかった。
今回の71A→ロクハンのコンビは、モコモコ・サウンドを吹き飛ばす勢いのある音で、全く驚きの連続である。なんだか昔年の埃を拭き取ったHi-Fiの王道を行くサウンドで、ちょっとしたジュークボックス感覚である。ポップ・コーンを頬張りながら聴くとさらにすばらしい。さらに収穫のあったのは、ビートルズのBBC音源とモッズの関わりが一気に開けたことである。ビートルズ以前の波乗りよろしく消え去った消費音楽を味わう。それも砂浜の貝殻集めではない、地引き網の生け捕り状態である。
|
| ②戦前のSP復刻 |
|
 |
ブラームス:交響曲第2・4番(1938・40年)
ウィレム・メンゲルベルク指揮/アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団
いつも思っていたのだが、誰が好きこのんでSP時代のオーケストラ録音を聴くのだろう? こういう疑問は常々持っていて、面白い演奏があっても普段から試聴するということはありませんでした。しかし今回この感想は全く覆されました。普通のモノラル録音として聴いても違和感がないばかりか、欠点と思っていたスタジオ用に小構成に絞られたオケの音は、貧弱どころか筋肉質に引き締まっており、音楽の推進力が非常に強い。
|
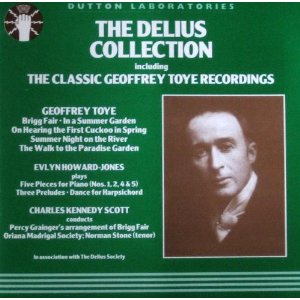 |
The Delius Collection(1938・40年)
Geoffrey Toye指揮
さらに難解なのがHMVのモヤモヤトーン。それも管弦楽となれば、録音がヘタだったのではという疑念が湧いてくる。ところがどうだろう、この奥行きのある深い音は。他の録音でも検証してみたが、クリーミーでいて音楽のon/offを切り替えられる録音は、むしろ繊細さに満ちていたのだと、ようやく理解できた。折り目正しいBTS規格との相性が良い例のひとつかもしれない。
|
 |
Biguine, Vol. 1 (1929-1940)
Biguine, Valse et Mazurka Creoles
これまで扱い方が難しかった戦前のラテン音楽。移民クレオールたちが奏でるビギンが、フランスで大人気を博したというのは、あまりピンと来ないかもしれない。世界恐慌の後の右翼勢力の台頭による政治的混乱に続き、1940年からのナチスドイツ占領により、パリのレビューを彩っていた移民色は一気に減退した。さらに戦後になると植民地の独立運動とともにシャンソン一色に染まったのだ(映画「シェルブールの雨傘」を観ると歴然としている)。その一時代を切り取ったこの録音は、フルレンジのモノラルで聴くと、色彩感の強い木管、シンプルでキレのいいパーカッション、おだやかな金管など、混血文化の粋が一気に見渡せる。どこからか音楽が聞こえ、次第に踊りの輪に加わっているかのような感覚にとらわれる。この押し付けがましさのなさは、ジャンゴ・ラインハルトにも通じる、ヨーロッピアン・ジャズの系譜に当てはまる。
|
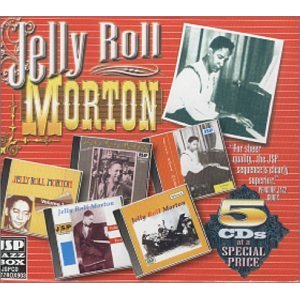 |
Jelly Roll Morton (1926-1930)
19世紀に流行ったラグタイムやケークウォークなど、現在では民俗音楽にジャンル分けされる、ボードビル系の演目を演じ続けた芸人の貴重な記録。ジャズの流行はすでに始まっていた時代でありながら、ブルースを通じた戦後のブラック・コンテンポラリーとの繋がりを考えると、今聴くとかえって新鮮に聞こえる。電気式の始まった頃の録音にしては、腰の据わった音色で、切っても切っても金太郎飴のような、べたな芸風をしっかり捉えている。しかし、ホーンがリラックスして歌う感覚は、今ではほとんど聴かれなくなったことを痛感する。
|
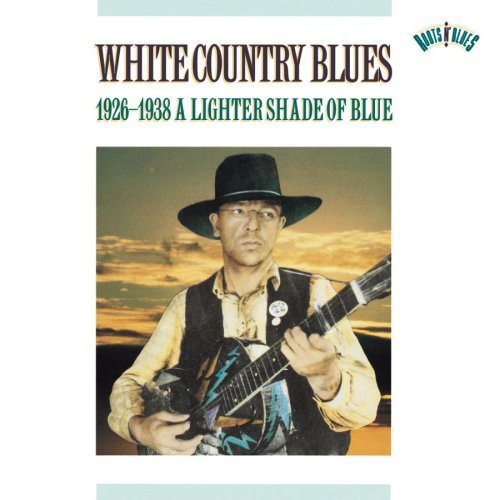 |
White Country Blues, 1926-1938: A Lighter Shade Of Blue
戦前ブルースというとただでさえキワモノ扱いされやすいのだが、このアルバムは白人のカントリー・ブルースに光をあてたキワモノ中のキワモノ。とはいえ、当時は過酷な労働条件の下で抑圧されていたアイリッシュなどが居たわけで、そうしたなかから現代に通じる極上の娯楽音楽が生まれたというのも全く嘘ではない。この録音集は当時の商業録音をピックアップして2枚のCDに収めたものだが、ブルース&アイリッシュ&ボードビル…スライドギター、フィドル、ハープ(ハーモニカ)、ヨーデルなど、創生期のカオス状態がエッセンスとして記録されている。南部音楽への差別的な扱いもあって、録音状態は必ずしも良好ではないが、ソニーがUSAの御旗を掲げての事業とあって、かなり力の入った復刻となっている。最初のスライドギターの一音から1929年という古さは全く感じられない。 |
| ③ラッパ吹き込み |
|
 |
Music from the New York Stage, Vol. 3 (1890-1920)
英Pearlの復刻は全く謎だらけである。貴重なSPのコレクションを継続して販売し続けるその意気込みとは正反対に、その復刻ポリシーというかサウンドは、押し並べて高域カットしたモコモコしたトーンで批判も多い。しかし改めてモノラル時代の放送グレードで固めたシステムで聴くと、これが非常に心地よい。この時代のボーカルは拡声器を使わないで肉声で演じていたため、ラッパ吹き込みでもしっかり入っている。ちなみ黒塗りの男は、ワーナー映画で最初のトーキーに登場したアル・ジョンソン。彼もミュージカルとボードビルの間を飛び跳ねて、しのぎを削っていた芸人のひとりであった。
|
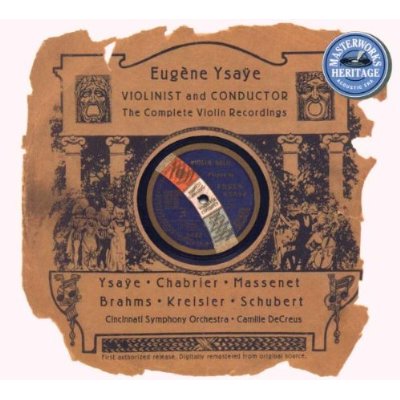 |
Eugene Ysaye Violinist & Conductor (1912-19)
フランコ・ベルギー派のヴァイオリストで、近代奏法の架け橋となったマエストロの貴重な記録である。しかし、ラッパ吹き込み時代のクラシックを演奏として鑑賞するとなるとどうだろうか? その答えがようやく見つかった感じがする。米Columbiaが自らのMaster
Worksに加えることになったこのCDには、ただ貴重なだけでは済まされない、レコードという文化への思いが詰まっている。そう、エジソンの発明から始まる、アメリカの古きよき時代の夢が詰まっているように思えるのだ。
|
| ④歌謡曲&フォーク |
|
 |
恋人もいないのに (1971)
シモンズ
大阪出身の清潔さ1000%の女性フォーク・デュエット。有名な表題曲のほかに、瀬尾一三、谷村新司が曲を提供するなど、この時代にしか為しえない贅沢な布陣で2人をバックアップしている。録音はジャケ絵そのままの「お花畑」状態のソフトフォーカスで、マンシーニ風の甘いストリングス、ポール・モーリア風のチェンバロまで登場する。このエコー感タップリの音場は、今のステレオ機器で聴くと、ボーカルは奥に引っ込み、直径1mを超えるビックマウスになるという、とても初歩的なところで躓いてしまう。当たり前だがモノラル&フルレンジは、この難所を軽々と乗り越えてしまう。そもそも喫茶店風の風合いが得意な組み合わせであるので、これはこれで耳が自然に受け入れてしまう。
|
 |
アドロ・サバの女王 (1973,75)
グラシェラ・スサーナ
当時は外タレとも言っていた外国人歌手。アルゼンチン出身のグラシェラ・スサーナは、一年に数人しかいない選ばれた存在である。歌唱力が日本人離れしているのは当前として、力で押し負かすのではなく、「誰もいない海」で魅せる静謐な歌い口は、むしろ日本人以上に日本語の美質にあふれている。このアルバムは優秀録音の典型で、アコースティック系のバンドの心憎い好サポートも相まって、どのシステムで聴いても深く破綻のない音が聴ける。で、なぜにモノラル&フルレンジなのかというと、上記のシモンズの録音と並べて比較しても違和感がない、そのことが凄いのだ。つまりスピーカーのもつ音響的な一貫性が、音楽をネグレクトすることなく自然に展開する。
|

