

���Q�O���I�I�EHi-Fi�����_�i�����P�R�j
�@�䂪�I�[�f�B�I���u�̓I�[�f�C�I�E�}�j�A����������D�G�^���̂��߂ł͂���܂���i�ʂɈ����^���̃}�j�A�ł͂Ȃ����B�B�B�j�B�I�[�f�B�I���̂��̎���̋L�����Đ����邽�߂̑��u�Ƃ������Ƃ������܂��B�����ł́A���m���������W�I�����p�̃T�u�V�X�e�����\�z�������ƂŁA�����̍D�݂Ƃ������̂ɐ����ɂȂ邱�Ƃ̑�������ݒ��߂Ă�����A�v�������܂܂Ƀ^���^���ƕ`���Ă��܂��B�܂��A���S�Y��ׂ��炸�Ƃ������A����Ήi���̏��S�҂Ȃ̂ł��`��B�B�B�B�̑O�ɒf���Ēu�������̂� 1)���́u�����}�j�A�v�ł���i�\�[�X�ۗL���̓��m�����F�X�e���I���P�F�P�ł��j 2)�Ɩ��p�@�ނɖڂ��Ȃ��i����^����������炩���܂��j 3)���C���̃X�s�[�J�[�̓V���O���R�[������{�łS����g�������Ă܂� 4)�f��A�A�j������D���ł���i70�N��̃e���r�܂ɓ��u��R�₵�Ă܂��j �Ƃ������قȖʂ������Ă܂��̂ŁA���̕ӂ͊�������ĉ{�����Ă��������B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���m�����~Low-Fi�ʼn��������I
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�y�䂪�t��Low-Fi�^���z �@�����g�̓I�[�f�B�I���D���ł���B��������������قǏ���ɂȂ��̂ŁA���ł��|�|�|���Ƒ�����킯�ɂ͂����Ȃ��B��������\�t�g���w������ق��ɂ������|����ق�������Ǝv���Ă���B����ʼn��t�͖ʔ����̂ɉ��̈����^���Ɉ����|�����������B�~���[�W�V���������U���|���Đ����������Ă���A������̐܊p�̃Z�b�V�������A�^�����C�ɓ���Ȃ��Ő�̂Ă�̂͂������ܑ̂Ȃ��̂��i�������CD����j�B�ŋ߂ƂɎv���Ă���̂́A�����̑�ʂ̃\�t�g���Y�i�ȂɌ��킹��S�~�̎R�j�����������E���̂��A�I�[�f�B�I�@��̖�ڂł���B���������������āA�Ƃ�����������������āA�������I�[�f�B�I�@��ɓ������Ă��鎟��ł���B�������r���[�ȋ@�ނ��W�߂Ă���̂ŁA���s�������B����Ŕ��Ȃ��ė��R���l����B�I�������������ŁACD�̍w�����܂��n�܂�B�������Ė������[�v��H��̂���Ȃ�ł͂̐��E�ł���B���������̕�����M���ǂ����痈���̂��H�@���͐����ȂƂ��날�܂�l�������Ƃ��Ȃ������B �@����̃��m�����@����������Ďv���o���Ă����̂��A�����̐N����̃I�[�f�B�I�̌��ł���B1980�N������LP�����̎���ł��������A���b�N��FEN�����iAM�j�̃E���t�}���E�W���b�N�⏬�э��玁�̃x�X�g�q�b�gUSA�Ƃ������ƂŁA��{���m�����ŕ����Ă������ƂɂȂ�B�E���t�}���E�W���b�N�́A���̃z���[�f���̃g�[�N�����邱�ƂȂ���A���\�Â����y�������ɗ����Ă��ꂽ��ƁA�v�������N���Ȃ̂��ȁH�@�Ǝv���Ă�����A35��1973�N�̉f��u�A�����J���E�O���t�B�e�B�v�Ŋ��ɂ��������L�����������Ă����炵���B1980�N��̃E���t�́A���͂��䏊���̑�䏊�ŁA���H�[���Ɖ��i�����邾���ł��ј\�\���Ƃ��������������B�ǂꂾ���L�����͒m��悵���Ȃ��������A�S�[���f���^�C���̂W���ɂȂ�ƓƂ蕔���ɂ������Ď����������̂��B  �@�����g���Ă������W�I�́A���ł�BCL���W�I�@TRYX-2000�B�Ȃ�ƂȂ��Z�g�����ɂ������������Ă����̂ł���B�{���̓i�V���i���̃N�[�K���~���������̂ł��邪�A���ł̋@�킪�X���Ŕ��z�������̂��w���B�ł��S�R���N���[�g�̃}���V�����Œ����Z�g�́A���܂��M�����ǂ��킯�ł��Ȃ��A�����ς�FEN���Ă����Ƃ������P�B���̃��W�I�͂����ƃg�[���E�R���g���[�����t���Ă��āA���̎�̃��W�I�Ƃ��Ă͉����������肵�Ă����B�{���ABCL�̓m�C�Y�̔ޕ��̉����������邽�߃w�b�h�z�����g���̂��ŁA�X�s�[�J�[�̓I�}�P�̂悤�ȋ@�킪�����̂����A�������̂悤�ȗ������ڂꃊ�X�i�[�̑������Ƃ�z�������A�Ɠd���[�J�[�Ȃ�̓ǂ݂��������̂��낤�B�X�e���I�ł͂����ς�FM���������A�X�e���I�Œ���AM�����̓{���������Ėʔ����Ȃ��̂ŁAAM�͂�����Œ����Ă����B���傤�Ǔy�j�̌ߌ��FM�����̖M�y���m�y��TOP10�ƁAFEN��TOP40���d�Ȃ邱�Ƃ������āAFM�̌��TOP40�̏��20�ʂ��āA�ŐV�`���[�g���`�F�b�N���Ă�����ł���B��͂�{��̃q�b�g�`���[�g���������āA���{�̂����蔽���������Ǝv���Ă������A���̓��W�I�P�Ƃ̂��̂Ȃ̂ŁA�r���{�[�h�E�`���[�g���Љ�Ă������j�̃x�X�g�q�b�gUSA���������Љ���Ȃ����������B����Ȃ���ȂŁA���j����y�j�͗m�y�O���������̂ł���B �@�����g���Ă������W�I�́A���ł�BCL���W�I�@TRYX-2000�B�Ȃ�ƂȂ��Z�g�����ɂ������������Ă����̂ł���B�{���̓i�V���i���̃N�[�K���~���������̂ł��邪�A���ł̋@�킪�X���Ŕ��z�������̂��w���B�ł��S�R���N���[�g�̃}���V�����Œ����Z�g�́A���܂��M�����ǂ��킯�ł��Ȃ��A�����ς�FEN���Ă����Ƃ������P�B���̃��W�I�͂����ƃg�[���E�R���g���[�����t���Ă��āA���̎�̃��W�I�Ƃ��Ă͉����������肵�Ă����B�{���ABCL�̓m�C�Y�̔ޕ��̉����������邽�߃w�b�h�z�����g���̂��ŁA�X�s�[�J�[�̓I�}�P�̂悤�ȋ@�킪�����̂����A�������̂悤�ȗ������ڂꃊ�X�i�[�̑������Ƃ�z�������A�Ɠd���[�J�[�Ȃ�̓ǂ݂��������̂��낤�B�X�e���I�ł͂����ς�FM���������A�X�e���I�Œ���AM�����̓{���������Ėʔ����Ȃ��̂ŁAAM�͂�����Œ����Ă����B���傤�Ǔy�j�̌ߌ��FM�����̖M�y���m�y��TOP10�ƁAFEN��TOP40���d�Ȃ邱�Ƃ������āAFM�̌��TOP40�̏��20�ʂ��āA�ŐV�`���[�g���`�F�b�N���Ă�����ł���B��͂�{��̃q�b�g�`���[�g���������āA���{�̂����蔽���������Ǝv���Ă������A���̓��W�I�P�Ƃ̂��̂Ȃ̂ŁA�r���{�[�h�E�`���[�g���Љ�Ă������j�̃x�X�g�q�b�gUSA���������Љ���Ȃ����������B����Ȃ���ȂŁA���j����y�j�͗m�y�O���������̂ł���B�@�̗w�Ȃɂ��܂苻�����Ȃ������̂́A�����ƍ���ԂȎႢ�����������̂ƁA�e���r�̃A�C�h���H�������܂�ʔ����Ȃ���������ł���B���j�����q�N���u�����A�����Z�����������A���܂�S�������Ȃ������ςȎ��ł��������B�܂Ƃ��Ȃ̂��I�t�R�[�X�A���E�~���A�����܂����A�Ƃ���Ε��͋C�����邾�낤���B���������N�z�Ȃ�I�[���i�C�g�E�j�b�|���ɂ�����t���ɂȂ��Ă�����������Ȃ����A�t�H�[�N�ɋ����������Ă�z�������ɕς��҂ŁA�ς��ғ��m�Ȃ�ƂȂ��g���������Ęb���Ă��悤�ȋC������B �@����ō��Z�ɓ���O�ɔ����Ă�������X�e���I�i�\�j�[�̃��V�[�o�[�j�����|���ŃN���V�b�N�ɋ������N�����B������LP�����S���������A�ŏ��Ɏ����̏������ōw�������̂́A�f�W�^�����^���ꂽ�e���[�N�^���̏��V�����́u�l�G�v�A�O�����t�H���^���̃W�����[�j�́u���C���v�������B�Ƃ��낪�N���V�b�N���y�������ƒm�肽�����߂ɍw�������u���R�[�h�|�p�v�̓��W�́A���Ɓu���j�I���ՂP�O�O�I�v�B���ꂪ�����̍����ŁA�Â����m�����^���������`���̖����Ƃ��ėL�����Ă��邱�ƂɐS�ꊴ�������B���e�͐[���m��Ȃ��Ă��L���ɗx�炳�ꂽ��C�̎���ł���B�����Ă��Ƀ����Q���x���N�^ACO�̃��C�u�^���Ɋ��S�ɎQ���Ă��܂����̂ł���B�^���̈����Ȃ�ꡂ��ɒ��z���������I�@�Ȃ�ƊÔ��ȋ������낤���I�@�����ٍ��̕������G�A�`�F�b�N����悤�ȁA���N���N�����C����LP�ɐj�𗎂Ƃ������Ă����B�Ȃ���NHK-FM�̒��̃o���b�N���V������̃��C�u�����������Ȃ������̂́A�����Â����������̗��ɂȂ��Ă�������B���͈������̖����́A�X�e���I���u�̑P���������Ė������蓾���Ƃ����I�`������i���ƍĔ̃��m�͐V����1/2�`1/3�Ƃ������ƂŁA���Z���̏������ɂ͒��x�ǂ������j�B �@�Ƃ������ƂŁACD�����ڌ������Ă�1980�N��ɁA���b�N�A�N���V�b�N����Low-Fi�ɐZ���Ă����N������߂����Ă������Ƃ����|���ŁA���̂悤�Ɉ������ə��߂Ȗ��͂�������̂ł��邪�A�v���Ȃ�����قǂɉ��y�ɏW���ł����̂����s�v�c���B�N���L�̊��̋����䂦�Ƃ������邪�A�����₷���N�������炱���ǂ����ւ̎v�����ЂƂ����������͂��B���ł����A�i���OLP�̓A���K�^�����邪�A�݂����R�[�h���Ɉ�����H�U��̗ǂ��Ȃ������̍�����LP�̉��́A������ȃv���X�ł���قǗǂ��Ƃ͎v��Ȃ������B�h���r�[B�̃J�Z�b�g�f�b�L�Ƀ_�r���O�����̂��̓}�V�Ƃ������x�̂��̂��B�Վ��Ɖ����������N���Ă��ĊS�����̂́A�ăo���g�[�N�E���R�[�h�i���������j��A��Ades�Ղ��炢�Ȃ��̂ł���B���̑��͐V���ł͂Ȃ��A�����ς牝�N�̖����t�̍w���ɖ������Ă����B����ł��ALow-Fi�Đ��ɂ̓m�X�^���W�b�N�Ȋ����ȏ�ɁA���t�ői���Ă���͂��B����Ă���Ǝv���̂��B���ʂ��ғ����������Ƃ��č��i�����ŕ������y���A�Ђ�����{���ɔ���c�̋����������Ă���A�����Ő����c��Ȃ����y�́c�ƁA�F�X�v�����炵�Ă݂�̂���l���낤�B �@����͌�Œm�������Ƃ����A����FEN�����ǂ��A���{�ł͒�����WE�@�ނ𑽐��g���������ǂ������Ƃ������Ƃ����������낤���H�@�P�ɗm�y�̕�����AM�ǂł͂Ȃ������̂ł���B���Ȃ݂Ɋ��疾���ɂ��ƁA1970�N�㏉����FEN�Ǘp���j�^�[�̓G���{�C��Georgian�������Ƃ����i�����̃~�b�h�o�X��SP8B���g���Ă���j�B�A���e�b�N�S������������ɂȂ�ƃA�����J���Ȍv�炢���낤���B����ƃG���{�C�̃X�s�[�J�[�̓A�����J�̃��W�I�ǂŌ��\�g���Ă��邱�Ƃ��������B��ԏ������ႢBaronet�����Ă����Ǝg���Ă��邶��Ȃ����I���́u�E���t�}���E�W���b�N��A���肪�Ƃ��I�v�Ɛ����Ɍ��������B
�y�傰���łȂ����m�����@�ނ��z �@�܂����f�肵�Ă��������́A�����ł̓��m�����Ƃ������Ƃňꊇ��ɂ���鑽�ʂȉ����iSP�ALP�A�����^���A�G�A�`�F�b�N�Aetc�j�ƁA�����t�������Ă�����V�X�e���\�z�̔��Y�^�ŁA�Ƃǂ̂܂胂�m��������̎�����ł���B �@���m�����̍Đ��Ƃ����ƁA�̂��牤�������݂���B�A���e�b�NA7��^���m�CAutograph�ɑ�\������^�X�s�[�J�[�𒆐S�Ƃ���A�{�i�I�ȃ��m������p�V�X�e���ł���B���𗁂т�悤�ɒ��������I�@�Ƃ����肢�����Ȃ�A���|�I�ȉ��������Ă���B�������A�@��̔�p�͂Ƃ����������̂ق��ɐ��{�R�X�g�̊|����̂���ł���B15�C���`�E�[�n�[�́A��r�I�傫��W�������Ă����Ȃ���Ζ肫��Ȃ��B�܂�傫�ȉ����ł��܂Ƃ��ɕ����镔���̃T�C�Y�̂ق��������Ƒ厖�Ȃ̂��B�����JBL�@D130�̂悤�ȁA�PW�ŏ\���ȉ�����������Ɛ�`���ꂽ���̂ł��A���ۂɂ͍���Ƃ̃o�����X�������Ė\��o���Ƃ������Ƃ�����B���x��C���ɂ���Ă����E����邨�V�C������Ȃ̂ł���B��������Ƃ����悤�ƃA���v���牽����q�[�g�A�b�v���Ă����̂��I�[�f�B�I�E�}�j�A�̏�ł���B�R�o��������Ȃ蒸����}���̂ł͂Ȃ��A���������͂��U�Ă���������Ȃ����낤���B �@�����ł�1940�`50�N��̕����^���ɏœ_�����ĂȂ���AHi-Fi�^���ɂ��Ώ��ł��郂�m�����@�ނɂ��ăg�s�b�N�X���܂Ƃ߂Ă݂��B
�@����ł͂P�`�Q�ɂ��āA�����Ȃ�̍l���������悤�B �y�`���̂W�C���`�E���j�b�g�z
�@���̃N���X��Rice & Kellogg��1925�N�ɊJ�������ƒ�p�_�C�i�~�b�N�E�X�s�[�J�[�̏����@����A�ƒ�ł̓d�C�Đ��Z�p�̗��j��w�������R������T�C�Y�ł���B���̃X�s�[�J�[�͉pBTH�A��AEG�ɂ��[�i����A����ΐ��E���̃��W�I�̏o���_�ɂȂ����B1939�N�ɃI���\�����m�ɂ���ĊJ�����ꂽRCA�̋Ǘp���j�^�[ MI-4400���A���r�����X�^�Ƃ������G�ȃo�b�N���[�h�z�[���������Ȃ���W�C���`�̃t�������W���g�p���Ă����B1947�N�Ƀ����[�X���ꂽWE 755A�́A�����p���j�^�[�̑��Ƀz�[�����[�X�i���W�I�ƃ��R�[�h�j�ɂ����z�I�ł����搂��Ă��āi�����AWE�Ђ̃z�[�����[�X�͂��ꂪ�B��ł���j�A���̃T�C�Y�̃��j�b�g���ǂ��ł��ō��̃N�I���e�B�ōĐ��ł��邱�Ƃ��������Ă���B�����͕����^���̃��j�^�[���疯���p�Ƀ_�E���T�C�Y����Ďg�p���Ă�����ԂƏd�Ȃ��Ă���B���ɐ��͌R���̗��ꂪ�ς���āA����Ε��a�Ҍ��Z�[���̂悤�ȏ���ȋZ�p���Y���c���Ă����Ǝv����B �@�W�C���`�̃t�������W�́A1950�N��̕č������j�b�g�����ł�WE 755A�AAltec 400B�A755E�AJBL D208�ALE8T�AJensen P8P�ATrusonic 80FR�AEV SP8B�Ȃǂ�����AWE 755A�ȊO�͂�������P�{5���~���x�ōw���ł��邵�A755A�͂��������v���J����������Ă���̂Ŋ��Ɏg���Ă���l�����邾�낤�B������̃��j�b�g�ł��A���͒����u�b�N�V�F���t����40�`60د�ق�����Ώ\���ŁA�o�X���t�A���͍D�݂ŗǂ��B�撣��Ί��̏�ɂ��\�����T�C�Y�ł���B �@�r���e�[�W�E���j�b�g�ł����90���̃T�[�r�X�G���A�ŋϓ��ɖ�̂ŁA�ǂ̊p�x���畷���Ă���a�����Ȃ��A�X�e���I�̂悤�Ɏ����ʒu�ɂ������Ȃ��Ă����B1m�ȓ��̃j�A�t�B�[���h�ŕ����ꍇ�ɂ��s�����ǂ��A���ۂɃ��W�I�ǂ̃��j�^�[���[���ɂ́A�g�[�N�o�b�N�ƌĂ��A���傤�ǍZ�������̂悤�ȉ����m�F���j�^�[�������āA���ł��u�[�X���̉�������悤�ɂ��Ă������B�Z�������Ƃ̈Ⴂ�́A�X�s�[�J�[����̋����ŁA���X2m�ȓ��ɂ͓����Ă��邱�ƁB���m�����������G�c�ł����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�l�Ƙb�����������傤�Ǘǂ��̂ł���B�W�C���`���j�b�g�͂��傤�ǐl�̊�̕��Ɏ��Ă��āA���Ȃ��牉�t�҂ɉ��y��ʂ��C���^�r���[�����Ă���悤�Ȋ����ɂȂ�B������X�s�[�J�[�Q�{�ōĐ�����Ɖ��̍L����͏o�邪�A�����͂����Ə������Ȃ��ۂ��ɂȂ�B �y�~�j���b�g�E�A���v�ƃR���v���b�T�[�z �@�W�C���`���ƃA���v�͂PW���̐^��ǃA���v�ł��\���ɂȂ�B�^��ǃA���v�̓N���b�v�|�C���g�܂ł�������点��̂ŁA�c�܂��Ȃ����߂̗]�T�x��K�v�Ƃ��Ȃ��B�Ⴆ��755A�p�Ǝv����e���r�����g�����Ɩ��p�g�����X���X�A���v�͏o��4�v�����A6V6�v�b�V����8W�A���v�͈ړ��f��ق̊Ȉ�PA�ɂ��g��ꂽ�B10W�̉����o�͂͗ߏ��ɖ��f�ȃ��x���ɂȂ�B���́A�~�j���b�g���ɂ͑f���̗ǂ����̂������A�o�͂̐�������I�[�f�B�I�p����h������Ă��镨���������A�\���̗ǂ��r���e�[�W�E���j�b�g�ł���Ώ\���ŁA�_�炩�߂̉��Ȃ�2A3�A45�A�X�����ȉ����D�݂Ȃ�6BQ8�iEL84�j�A71�A�i�`�������u���Ȃ�6V6�A6F6�Ȃǂ�����B����90��B/w/m�������}���`�E�F�C�E�X�s�[�J�[�Ȃ�KT88�A6L6�A300B�Ƃ��������߂̋��łȂ��ƃE�[�n�[���o�����X�ǂ���Ȃ����A95dB�ȏ�̃t�������W�͂��������S�z���Ȃ����肩�A�ނ��냀�b�c���Ɠ������Ȃ��Ȃ銴��������B�����A���܂�ɏ��o�͂Ȃ̂ŋ��̋쓮�|�C���g�������Ă��Ȃ����߁A���y�̖��������o�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���BNFB�̂����߂��������������邽�ߗv���ӂ��낤�B �@���ƃ~�j���b�g�E�A���v���g���Ă��ĕ֗����Ǝv�����̂��R���v���b�T�[�B�ʏ�͐��y��̃_�C�i�~�b�N�X�𐮂��邱�ƂɎg�����Ƃ������̂ŁA���ɐ�������̘^���ɂ͕K�v�Ȃ��Ƃ����̂�����̈ӌ����낤�B�������ŋ߂̃��}�X�^�[CD�́A�I���W�i���E�e�[�v���璼�ڃ_�r���O���ĕҏW���邱�Ƃ��������ACD�̂ق����I�[�o�[�X�y�b�N���Ǝv���Ă���̂��A�_�C�i�~�b�N�����W�Ɋւ���R���g���[���́A�����X���ɂ��邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B�s�A�m����t�H���e�܂ł̕����\�[�X�̍ő���łƂ��Ă��邽�߁A�s�A�m�ł̉��ʂ��������̂Ń{�����[�����グ��ƁA�t�H���e�ŏ��o�̓A���v���N���b�v���ĎG�ȉ��ɂȂ�B���̉��ʍ��𐮂��Ă�����̂��R���v���b�T�[�ł���B�����Ɏg���Ă݂��̂�Behringer Autocom MDX-1200�Ƃ�������܂����������A�����Ǝd�������Ă����̂ŏd�Ă���B�X���b�V�����h�̓~�L�T�[�̃Q�C���Ƒ��ΓI�Ȃ̂ŎQ�l�ɂȂ�Ȃ����|20dBu�A���V�I��1�F4�A�A�^�b�N100ms�A�����[�X0.5s���炢�����傤�Ǘǂ��B�悭�A�i���O�̃R���v���b�T�[���|����ƍ��悪�݂�Ƃ������ۂ��N���邪�A8kHz���x�̃����W�ł͂قƂ�NjC�ɂȂ�Ȃ��B���ƂȂ��v���o�����̂́A�̂�MM�J�[�g���b�W�̉��ŁA�����J�[�g���b�W���̂��̂����C�q�X�e���V�X������̂ŁA�R���v���b�T�[���|�������悤�Ȋ����ɂȂ��Ă�����������Ȃ��B�������̓��b�J�[�Ղ̃J�b�e�B���O���Ɏg�p���Ă����R���v���b�T�[�������悤�Ȑ��i���������Ă���̂�������Ȃ��B�t���g���F���O���[�̃x�������ł̃��C�u�́A���̃��~�b�^�[�̕Ȃ������āA�t�Ƀ_�C�i�~�b�N�ə��Ⴗ�邵�A�r�[�g���Y��BBC���C�u�ł̓h�������r�V�o�V��n�߂�B���̎�̕����^���ł͎��R�ȃA�R�[�X�e�B�b�N�ɂ������K�v���͂��܂�Ȃ��悤�Ɏv���B �@���ꂪSP�^�����ɍ��킹��1920�N��̃��W�I�g�����X���g���ƁA���Ƃ��ƃg�����X�̉��̗����オ�肪�݂��������A�A�^�b�N100ms�A�����[�X1s�ӂ�ʼn��̃X�s�[�h���������Ă���B�����ĖF���ȉ����ڂ��Ă���Ƃ����I�}�P������A�R���v���b�T�[�����͂������������Ƃ����邾�낤�B �y�g�[���R���g���[���ƃg�����X�z �@���m�����^���̓��[�x�����̉��������l����ƁA�ǂ����Ă��A���v�̃g�[���R���g���[���͕K�{���Ǝv���B�̂̃A���v�Ȃ��ɕt���Ă����g�[���R���g���[���́A����LP�̃C�R���C�U�[�J�[�u�̈Ⴂ���C��������̂������ɂ���A���m��������̑��l�ȃg�[���̈Ⴂ���C�����邽�߂ɂ͕K�v���Ǝv���Ă���B���ꂪ�����@�ނ������Ă���Ȃ�A�^���p�@�ނƂ��Ĕ����Ă���EQ�t�̃~�L�T�[���A��p�C�R���C�U�[���ԂɊ��܂����ق��������ƗZ�ʂ������B���^�~�L�T�[�́A�������̂Ȃ�P���~�����̂����邵�A�X�e���I�����̃��m�~�b�N�X�ɂ��g����̂ŁA�ӊO�ɏd��B �@IC�`�b�v�Ōł߂�ꂽCD��~�L�T�[�̖��C�Ȃ��Ƃ���́A���C���g�����X�ȂǂōI�����K�����킹���B�����̃v���A���v�Ŏg����MT�ǂ̑f�n�͋ɂ߂�Hi-Fi�ŁA�r���e�[�W�̃A���v��Input���邢��Output�g�����X�̖��t���ʼn����߂�����Ă��邱�Ƃ������B���̂��߈�ʓI�ȃn�C�E�C���s�[�_���X�n���̊Ԃ��A�����̃g�����X�łȂ���Ηǂ����ƂɂȂ�B�s�A���X�ł���Αf����Hi-Fi���̂܂܂ʼn��̉����o�����ς�邵�A���̂悤�ɕω������߂ċ����ш�̂��̂��g���̂��D�݂̖��ł���B �@�ȉ��͗��Z���܂߂āA�G���{�C��SP8B�ɍ��킹���Ƃ��́A�g�����X�ƃC�R���C�U�[�̑g�ݍ��킹��������BSP8B������ȍ���������Ă��āA�i�`���������Ƃ��Ȃ�L�c�C���ɂȂ�̂ŁA�m�[�}���ȉ��ł�����͗}���C���ł���B�����UTC���̃g�����X��10kHz����ɂ₩�Ƀ��[���I�t����^�C�v�ŁA��������邱�ƂŊ����C���̃G���{�C�̉��ɃE�F�b�g�Ȏ����������B����ł��S���}�����Ȃ�Decca ffrr�̂悤�ȍ���̋����^���́A�t��5kHz���烍�[���I�t����1920�N��̃��W�I�p�g�����X�iLissen�Ё@Hypernik�j�ō����啝�ɃJ�b�g���Ă���t�Ƀu�[�X�g���Ă��B�ǂ������킯���A����Ŗ��̂悤�ɊÂ��f�b�J�E�T�E���h��������B���͐�O�̘^�����A�A�B�̑S���Ⴄ�A�v���[�`�ŕ�����ׂ�ƁA�g�[���ɂقƂ�Ǖω����Ȃ��̂ŁA����8kHz�܂ł̃g�[���͂قƂ�Ǔ����ł��邱�Ƃ�����BDecca ffrr�͒�����4�`6kHz�̕ӂ�ɋ����s�[�N���������āA���ʂ̃t�������W�Ȃ�p�����ƃ��[���I�t���₷���ш�����ėǂ��v���[���X�����邪�A���ɂ��̑ш���u�[�X�g���Ă���G���{�C�̃��j�b�g�ł͋t��ŁA�݂��̎咣���I���L�����Z������K�v������B�������Decca ffrr��CD�R���N�V�����͏��Ȃ��̂ŁA�ނ����O�̘^�����I����������G���{�C�̒����̂ق����L�����̂Ɣ��f�����B
�@���͂����̓�����WE�`Altec�̗��h�ł����ƁA�@��WE 755A�A�A��Altec 400B�ɋߎ����Ă���B������������p���j�^�[�Ƃ��ĊJ�����ꂽ���̂ŁA������1947�N��1945�N�Ƌ͂�2�N�̍��ł��邪�AHi-Fi�@��̖����������ɂ��������̈Ⴂ���悭�\���Ă���B�t�H�[�}�b�g�ł�����SP�Ղ�LP�̃g�[���̈Ⴂ�������Ă���悤�ɂ݂��邪�A�����̃A�Z�e�[�g�^���@�ł�8kHz�͗D�ɒB���Ă���̂ŁA�ނ�����^���̌X����Hi-Fi�ȑO�ɂ�3�`6kHz���������Ă����iMarconi-Reisz���J�[�{���}�C�N��1935�N���܂ŕ����ǂŊ��Ă����j���Ƃ��f����B�����炭1941�N��FM�������J�n���ꂽ���́A�ƒ��Hi-Fi�Đ��ł���\�[�X�����W�I�ȊO�ɂȂ��A��ʉƒ�ł͉��b�ɗ^�邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ������Ǝv����B���̂��߁A�Ⴆ�����R�[����WE 750�Ȃǂ̍����\�X�s�[�J�[�͎��p�I�ł͂Ȃ������\���������B���̈Ӗ��ł́A400B�̂悤�ȌÂ����C�h�����W�E���j�b�g�́A�P���ȃJ�}�{�R�^�Ȃ̂ł͂Ȃ��A10kHz�܂ōĐ���ۏႵ���m�M�ƓI�ȓ����ł��邱�Ƃ�����B�����l������RCA MI-4400�i���r�����X���A1939�N�J���j�ɂ��Ă������A�����GE�Ђ�Rice & Kellogg�����E�h�X�s�[�J�[�����P���Ȃ�������p���ꂽ�`���I�ȓ����ł���B �@Hi-Fi�^���ɍ��킹�ăt���b�g�Ɏ����グ�邱�Ƃ������S�Ăł͂Ȃ��AAM�����̋K�i���M���M���̂Ƃ���Œ����x�▾�Đ����m�ۂ��悤�Ƃ������j�I�o�܂�ق��Ă������Ƃ��K�v���B����͏����̈���PA�@��̕���ŏ펯�Ƃ��Ēm������e�ŁA����Shure�Ђ̃{�[�J���}�C�N�����C�u���ŏd���̂́A�q�����N���A�ɏW���ł���Ƃ��������Ƃ������R������̂��B
�@���ǂ̂Ƃ���A����̏o������ŃR���R���ς��ȏ�A�Đ����̍œK���Ƃ����̂̓C�^�`�������ł���A�ӂ��̓�����p�ӂ��邱�Ƃ��̗v�ƂȂ�B�Ƃ��낪��ʓI�ɂQ������ƂȂ�ƁAHi-Fi�p���S�[�W���X�ɖc�ꂠ����X�����ۂ߂��ASP�Ղ͂��납���W�I�����p���҂�s�����Ƃ�����͂��܂蕷���Ȃ��B�t�ɗ��҂��ꏏ�ɂ���Ƃǂ��炩���]���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�Ɏv����������Ȃ����A�������������ʼn��t���r�ł��邱�Ƃ������炷�K���͉����ɂ��ウ����낤�BHi-Fi�ɂ����ڂ������Ă���ƁA1950�N������Ƀ~���[�W�b�N�E�V�[�����K�����ƕς�����悤�Ɋ������邪�A����̓��W�I������m��Ȃ����Ƃɂ����o���ƌ��悤�ɂȂ�̂�����B �y���悪�S�ā`�����f�̗��z �@�R�Ԗڂɐ��_�_�Ə������̂́A�n�[�h�E�F�A�̐����ȏ�Ƀf���P�[�g�Ő������K�v�Ȃ̂́A������̃����^���ʂł���Ǝv��������B���ɋ���������A�����̒��S���ǂ��ɂ���A����ڎw���Ă��邩�A�������������ʒu�ƃI�[�f�B�I�͂ƂĂ�����Ǝv���B�I�̏Z�ݏ�����^�z�[���V�X�e���ɂȂ�̂��A�t�������W�ɂȂ�̂��́A���͂��̐l���̐l�̏���Ȃ̂��Ǝv���B��͂�I�[�f�B�I�E�V�X�e���̍\�z�̂Ȃ��Ƀ��C�t�X�^�C�����Ȃ��ƒ��������Ȃ��B���m�����ƕt����������ɂ́A�̂�т�\����Ƃ������A�Ǎ����Ƃ������̂��K�v�Ȃ̂����A���������_�I�ȗv�f�ɉ����Ă��ǂ��B�������A�C�\���Ƃ������S���͂��̎����̎��̂��̂ł���A�����ڂŌ���ƁA�Ƃǂ̂܂胉�C�t�X�^�C���ɍs�������̂��B �@�����̍œK���������^���ȕ����Ɋ܂߂��̂́A���m���������̑傫�ȕǂł���Hi-Fi�ȑO�̉����̈����ɂ��āA�ǂ����Ă�8kHz�̕ǂ���蕥��Ȃ��ƃR���N�V�����̊u���肪�����邽�߂��B�����炭1950�N��ł����ALP�Ń����[�X���ꂽ���̂͑S�Ẳ�����10%���x�������Ǝv���A���R�[�h�ƊE�ƃ��W�I�ƊE�̎���̊u���������B�l�I�ɂ́A���y��i�Ƃ��Ċӏ܂���̂̓��R�[�h�A�~���[�W�V�����̉��t�e�N�j�b�N��^�����g��m�肽���̂ł�����W�I�����Ǝv���Ă���B�ӂ������Ďn�߂Ĉ�l�O�Ǝv���̂��B�܂��e���r�̂Ȃ�����A���҂��ꏏ�ɕ��������������̐l�́A�ǂ������Ă����̂��낤���H�@���̕����ƒ�ɂ͂��߂āu�X�e���I�v���}����1970�N�����́A����AM�����̓����W�������ߋ��̂��̂ƂȂ��Ă����B���ʂɃ��W�I�Œ����Ă����ق����f���ɖ��Ă����悤�Ɏv�����A�u���R�[�h��FM�̓X�e���I�Łv�Ƃ������o�����荞�܂�Ă����̂��������B����ł��e���r��r�f�I��AM���̃����W���������Ƃ��l����ƁA"�X�e���I"�łȂ��Ă������W�����C�ɂȂ�Ȃ��������������̂��B���ꂪ�����20�N�k��1950�N��͂�������Hi-Fi�����Ƃ̏s�ʂ̏����i�K�ɂ������ƍl���č����x���Ȃ��B �@�ŋߋC�t�����̂́A���̎���̃I�[�f�B�I�I�ȃ��A���e�B���@���ɍ�蕨�߂��������Ƃ������ƁB�����͉��ł��������Ŗ��Ă���悤�Ɋy�����߂��Ɉ����Ă���邵�A�ቹ�͂��ꂾ���Ŕ��͂���芴��^����B�����nj��ǂ́A���y��ʂ��ăR�~���j�P�[�V���������A�S��ʂ������Ƃ����̂́A�����������O�ʓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��͂����B�ނ���A���T���u�����炱�ݏグ������̗��ݍ����Ƃ������A����ł̃^�C�~���O��f���i�[�~�N�Ȃǂ̍��i���d�v�Ȃ̂��Ǝv���B���ƌ����Ă����y�̃t�B�W�J���ȕ�����100�`1000Hz�̒���ɖ��W���Ă���̂��B �@���m�����^���́A���̓_���P�{�����ŃX�g���[�g�Ȃ̂��B�悭�W���Y�̓��m�������オ��ԂƂ����������A�N���V�b�N�����āA�|�s�����[���y�����āA���̓��m�������ʔ����B����͉��y�I�Ȗ{���̕������A���̃X�^���X�ň��肵�Ē����邱�Ƃ��K�����Ă���Ǝv���B���́u���̃X�^���X�v�Ƃ́A���m��������̊g���Z�p���APA�@��̃m�E�n�E��s�f�Ɏg���āA�I�[�v���Ȍ������������Ă���Ƃ����_�ł���B���ꂪ���W�I�Ƃ����ƒ�p�@��ɂ�����Ă���BPA�@��Ƃ����ƁA���b�p�g���@��Z�������̂悤�ȋɒ[�ȗ���v�������ׂ邩������Ȃ����A���o�͂̃A���v�Ō����悭�`�B����m�E�n�E�Ƃ����Ɣ���₷���Ǝv���B���̂��߂̃X�s�[�J�[�𒆐S�Ƃ��鉹���Z�p�́A����Hi-Fi�̏펯�̗��������悤�ȂƂ��낪����̂ŁA��x�悭���ݍӂ��K�v������B�܂�AM�����Ɠ���80Hz�`8kHz�i���ꂪ1932�N WE�Ђ�Wide Range System�Ɠ����j�Ƃ����K�v�ш�̘g���ł̉��t�Z�p�̔��W�j������A1925�N�̓d�C�^���J�n����1950�N���LP���R�[�h�܂ł̎l�����I�Ɍׂ鑽�l�ȃg�[��������B���ʂ̐l�Ȃ炱�����T���B�ʓ|�L���̂Ŕ�Hi-Fi�Ƃ�������ŕ\������B�������A���̌�����x�����J����ƁA���肵�������Z�p�Ɏx����ꂽ�A�₩�ȃ��r���[�̐��E���h��̂ł���B �@���ۂ�8kHz�����E�Ƃ����Đ����Ƃ͂ǂ��������̂ł��낤���H�@���͎s�̂̑����̃X�s�[�J�[�́A8kHz�܂Ńr�b�`���Ɩڂ��l�����o���Ă�����̂͏��Ȃ��B�قƂ�ǂ͋p��30�x���t���ƍ��悪�������n�߂�B����̓t���b�g��BBC���j�^�[�ł�5�`6kHz�ӂ肩��A�������������ƂȂ����^���m�C�Ƃ��Ȃ��2.5kHz���猸������B����ŁA����̊g�U������������Ă��āA8kHz�܂ł�������o�Ă���PA�p�̃z�[���X�s�[�J�[�́A���悪�L�c�C���炢�o�Ă���Ɗ�����B�Ƃ������˂��h���Ă���悤�ɒ��ډ��Ŕ����Ă���B����͓����̋K�i��30ft�i��9m�j����Ă�����̃T�[�r�X�G���A��ۏ��悤�Ƃ������ʂł����āA���{�̈�ʉƒ�̂悤��2m�ȓ��Œ����Ƃ��ɂ́A�����܂ł̉����G�l���M�[��K�v�Ƃ��Ȃ����A�������������ꂪ�Ȃ��Ȃ�̂��B�ނ��둽���������Ă���邭�炢���S�n�ǂ��̂ł���BJBL�����ĉƒ�p�̃z�[���V�X�e���́A�������Ƀr�[�����C�Y�𗎂Ƃ��Ă���B���̂悤��8kHz�܂ł̘^���i���Ƃ́A�펯�I�Ȕ͈͂ł̍Đ��̈�Ƃ����āA���̑ш�̖��x�ʼn��y�̎����ς��Ƃ�������B �@�Ⴆ�A����~�������X�e���I�T�E���h��36���i1975�N9���j�́u���W�E�w�X�s�[�J�[�V�X�e���̂��ׂāi��j�x�v�ł́A�V�A�^�[�p�X�s�[�J�[�ɂ��āu���݂̍������x�i�n�C�t�B�f���e�B�j�̋Z�p����݂�A�V�A�^�[�X�s�[�J�[�͂��͂�L�ш�Ƃ͌����Č����Ȃ��B���������̂��Ƃ���t�ɁA���y��l�̐��������������������邽�߂ɂ́A�����čL�����g�������W���K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ�m���Ă������Ƃ͖��ʂł͂Ȃ��B�ቹ��80�w���c�A�������V�`�W�L���w���c�B���̒��x�̑ш��{���Ɏ��̗ǂ����Ŗ炷���Ƃ��ł���A�l�Ԃ̎��͂���𑊓��ɗǂ������Ɗ����邱�Ƃ��ł���B�v�Əq�ׂĂ���B����͓������C�Ȃ����ɂ��Ă�������i���̉����Z�p�Ƌ��ʂ������̂ł��邪�A�����ш���ɓ����������ʂ̃��x���������������@�ނ𑵂��A�������d�C�I�ȉ��H�̏��Ȃ��~�b�N�X�Œ�����̂��A���m��������̑傫�ȃA�h�o���e�[�W�ł���B �@���ꂪ�X�e���I���ƁA�܂��T�E���h�E�X�e�[�W�̂Ȃ��Ŋy�킪�z�u����A����Ƀ��[���E�G�R�[�ɂ���ċ�Ԃ̍L�����\�������B����������́A���ۂɂ͉ˋ�̋�Ԑݒ�ł���A�����G���W�j�A�̕��j�ɂ���ċ�Ԑݒ�̓o���o���ŁA���̕��䂪�����Ɩ{���̉��t�̃o�����X������Ȃ��Ȃ�B�P�ɒቹ�`�����̃o�����X�����ł͌��s�����Ȃ��A���G�ȗv�f������ł��āA�����ȃI�[�f�B�I�ɂȂ�قǁA�����̑����̖��͂����t���܂Ƃ��B�W���Y�͉��ꂪ�L���Ă͍��邵�A�N���V�b�N�͍��悪���邳���Ă͍���B�������ĉ���̕��͋C�ɓۂ܂�āA���i�̕����ȊO�̂Ƃ�����T���v�f�������̂ł���B �@�����āA�c�C�[�^�[�̉����̂��͔̂��ɏ������������x���i1kHz�ɑ�10kHz�ȏ�́|20dB�ȉ��j�Ȃ̂ɑ��A�X�s�[�J�[�̓�����A�U���̌y�������̂ق������X�|���X�������A�S�Ă̑ш��葁�����ɓ��B����B���ꂪ�}�X�L���O���ʂƂȂ�A�c�C�[�^�[�̌����≹�����A�����T�E���h�̌X��������t����Ƃ����A�t���܂̏����܂��B����̓c�C�[�^�[�̏o������Ɏx�z���ꂽ�I�[�f�B�I�ŁA���ۂ̉��t�̃_�C�i�~�Y�������A�p���X�g�̎��ʼn��f����Ȃ����ɕt���Ă��܂��B���ꂪ�����S���w�ƌĂ�镪��̐��ʂł���A20���I�̓d�C�����Z�p�̊�{�I�ȍl�����ł���B �@�^����\�ʓI�ȉ����]�����瓥�ݍ���ŕ������݂����Ƃ��A����������Đ���Ƃ��K�v���Ǝv���̂��B�����Ŏv�����ĉ�����\������ш�A10kHz�ȏ�����Ă݂悤�Ǝ��݂��B
�@����Ȃ���ȂŁA���ǁA�R�����ɂ���ԍ����̒f�̗��̌��ʁA���悾���ŏ\���ɉ�����c���ł��鎨���ł����������B�����Ȃ�ƁA���y�̕]���͑S���ȑO�ƈقȂ�A�L����炩�ɂȂ����B�����ăT�E���h�ɑ��銴�����A�ȑO�ɂ������ă\�t�g�E�F�A�����t�Ҋ��ɂȂ����B�悤����Ƀn�[�h�E�F�A���@�ނ��A���R���l���Ē������Ƃ������Ȃ��Ă����B����ɉ����A�^���̍D�������ɂ���āA�����������ȉ��t�Ƃ����̂����Ȃ��Ȃ��Ă����B �y���W�I�������ؗ�Ƀ��r���[�z �@�Đ����u���ǂ����~�ŋO���ɏ�����Ƃ���ŁA�ŏI�ړI�̃A�[�J�C���̎d�����ł���B���͍Đ��@��Ɖ����̃A�[�J�C���́A�{�Ɨ��̊W�ɂ���A�Đ����u���悩�A�[�J�C�����悩�Ƃ����D��x�͂Ȃ��A�ǂ��������������10�N��ɂ͑e��S�~�Ɖ����Ă��܂��B �@�������A�܂��ŏ��ɋ�s�����킹�Ăق����B�I�[�f�B�I���D�Ƃ��A���m��������̃��W�I������^���Ɏ��g��Œ����Ƃ������Ƃ́A�c�O�Ȃ���قƂ�Ǖ����Ȃ��B���W�I�����̂��߂̍Đ����u���ǂ�����ׂ����H�@����͋��Ȃ̂ł���B�I�[�f�B�I�D���̐l�́A�Ƃ������W�I��ډ�����B�u���W�I�݂����ȉ��v�Ƃ����ƁA���̑��u���J�}�{�R�^�̔�Hi-Fi�I�ȉ����w���B��ł���B�قƂ�ǂ̐l���A�����̃t�������W�����^�^��ǂŖ点�Ύ������Ǝv���Ă���B���������A���{���̈����ۂ����W�I�����m��Ȃ��̂����ł��邱�Ƃ���낤�Ƃ��Ȃ��B100�`6,000Hz�Ƃ���AM�����̋K�i���ł��A100�`2,000Hz��2,000�`5,000Hz�̑ш���X�s�[�h���������āA��������点��V�X�e���Ƃ����͈̂ӊO�ɓ���B���̑ш悾���ʼn��y�\���̍������߂Ă���A�����W�������Ō떂�����������Ȃ��A��{�����ő��荞�܂ꂽ���j�b�g�������e�҂ƂȂ�B �@JBL��D130�����߂Ƃ���1940�N��̃��C�h�����W�E���j�b�g���A���݂�Hi-Fi�@��̊�ł͒P�̂ł̕]����������j�b�g�̂ЂƂł���B�uSP�^���ɂ͑������ǂ��v�Ƃ��������ɁA���ɗǂ��\�����Ȃ����̂��낤���H�@���������̕]���̊�́A������PA�p�A���v�A�J�[�g���b�W�AAM�����Ȃǂ̋��K�i�Ɉ͂܂�Ȃ���A�ō��̉�����悤�Ƃ������Ƃ������ł��Ȃ����Ƃɂ��B�Ƃ�����1945�`49�N�̘^���ƍĐ��@��͈�ʂ̃I�[�f�B�I��]�ł͕]�����ǂ��Ȃ��̂ł���B����͐���Hi-Fi�@��̔��荞�ݎ��ɍ��荞�܂ꂽ���̂ŁAGE�̃o�������ł��������̃I�[�f�B�I���ł́A�����ǂŃA�Z�e�[�g�Ղ��Đ����邽�߂ɃX�y�b�N���Ⴂ�̂��Ɛ��������n���������B����������̓��`���W�����b�Əo�銴�o�́A��x���키�ƕa�݂��ɂȂ���̂�����B����ƁA���̎���ɑs�N�����}�����~���[�W�V�����͈Í�����̏Z�l�ł͂Ȃ��A�ނ��냉�W�I��ʂ��ăA�����J���y�̃X�^�C����z���グ���l�X�ŁA�����m�炸���ăA�����J���y�̗��j�����ׂ��炸�A�Ƃ������q�ł���B�����Ă��̃p���h���̔����J���錮��Hi-Fi�ȑO�̋��K�i�Ő������ꂽ�I�[�f�B�I�@��ł���B
�@���W�I�͒N�ł��^�_�ŕ����邩��Ƃ������R�ŁA�킴�킴�������o�����l�̂Ȃ����́������Ƃ������b�e��������B���ꂪ���������̊ԈႢ�Ȃ̂ł����āA���͕����ƊE�قǂ����̊|����ƊE������قǂȂ��ł��낤�B�l�I�ɂ̓��W�I�����́A�i���Ɍ��������K�ȍĐ����@�������ƂŁA���{���̖��͂��������̂ƐM���Ă�܂Ȃ��B���ꂱ���A�N�����[���̂������ϓI�ȕi��������Ă�������ł���B�t�ɂ����ƁA�I�[�f�B�I�I�ȉ��Ƃ́A���W�I�̕i�����傫�����킷����̂łȂ���Ȃ炸�A�����ɂ͂��̎肱�̎�̑n�ӍH�v�������Ă��āA�Ƃ��ɂ͊��傫���O��邱�ƂŔ��荞�����Ƃ���B���̃f�t�H�����̋���I�[�f�B�I���u�̑����̖����Y�ݏo���Ă���悤�Ɏv���B���̈Ӗ��ł́A�N���V�b�N���W���Y�����b�N���A�����p�̃��W�I�Ƃ����̂͑��݂��Ȃ��̂Ɠ����悤�ɁA���W�I�����������r�F�̂Ȃ������̃X�^���_�[�h�ȉ����蓾��̂ł���B �@�������A���W�I�p�Ɏ��^���ꂽ���m���������ɂ��ẮA�I�[�f�B�I�I�ɂ��A���y��Y�Ƃ��Ă��A�ǂ������ʒu�t�������ėǂ��̂����܂蔻��Ȃ��B�قƂ�ǂ͂Ԃ����{�Ԃ̃����e�C�N���^�B�X�^�W�I�̂悤�ɉ��x���^�蒼������A�_�u���d�˂Ďd�グ�����邱�Ƃ����Ȃ��B�i���K���ɂ���Ď��^�����܂������@�Ř^���邽�߁A�����͂��G���̋����N�[�����̂��́B�Ȃ��ɂ́A�~���[�W�V�����̃^�����g�������������C�h�V���E������A�t�@���ɂƂ��Ă͊���Ȃ���i�ɂȂ邾�낤�B�������A�Ȃ��ɂ̓G�A�`�F�b�N���܂ފC���Ձi�u�[�g���b�O�j�̑��݂��i�̖�������������Ƃ���������B���ꂪ���W�I�����p�̉������J��Ԃ���������ꍇ�ɁA��ɕt���Z���]���̓���ł���B �@���W�I�̕�����l����ƁA�ĕ҂���Ĕ��������CD�́A�V���L���̃X�N���b�v�̂悤�ł�����A�m���ɂ���������̈�[�ł͂��邪�A����ō�i�Ƃ��Ă̊����x����ꂽ�ꍇ�A���ꂪ�~���[�W�V�����̍ŏI�I�Ȍ��_�ł��Ƃ͌�����B�������A�������̂�������l�ԂɁA���ł��ō��Ƃ����^�����K�v���낤���H�@�ہA���������_���݉z���ă��W�I�o�������~���[�W�V�����̋L�^�Ƃ��đ�Ȃ̂ł���B�����ėǂ������^���ɂ́A���̎���A���̎��Ԃɂ����������Ȃ������}�W�b�N������B �@����Ȃ���Ȃő~���W�߂��A�ȉ��̃R���N�V�����𑍍��I�ɂ݂�ƁA���W�I�����̂��Q�X�g�̍L�͂��A�^�C�g���̑����ɋC�t�����낤�B�����A���鉹�y����A�~���[�W�V�����̃f�B�X�R�O���t�B�[�ȂǂŐ蕪����ꂽ��]�Ɋ��ꂽ�l�ɂ́A�����p�����ɓ����������t�j�A�^���Z�p�j���A����܂ł̍�i���ނɊY�����Ȃ��������Ƃ�����͂��ł���B�]�����x�ꂽ���R�́A�قƂ�ǂ͕����������߂���Ɠ�x�ƒ�����邱�Ƃ��Ȃ��������߂��i���ƃ��W�I�������������蓾���ԑg�X�|���T�[�̗�������������������Ȃ��j�B�܂��A���C�u�^���𐳋K�^���̕⑫�Ƃ��čl��������̑������Ƃ��m�����B�������A���������Ԏ���ɕ��ׂ�ƁA���t�j�̎����̐��X�������яオ���Ă���B�^���̎������A���ꂼ�ꂪ�����j�I�ȃo�b�N�{�[���̖L�����̂ق����Aꡂ��ɏ����Ă���_���������Ȃ��B�����������^���̕i���𐳂����]�����邱�ƂŁA����ׂ��p�������яオ���Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��K�v�ł��낤�B�����܂ł����㖈�̋Z�p�I���E�̂Ȃ��ŁA�K�ȉ����̘g�g�݂�^���Ă����邱�Ƃŕ]�������₷���Ȃ�̂��B�����^���̏ꍇ�́A���ꂪ���W�I�ƂȂ�B�������̘g�g�݂ɗ^����ꂽ���l�����A����܂őz�����Ă�����肸���ƍL�͂Ȃ̂��B�܂��Ɏ���̕������̂��̂ƌ����Ă����A�ؗ�ȃ��r���[�������オ��̂��B �@
�@�����������̂�ǂ�ŁA�����i���u�H�j���N�����Ȃ�A���АF�X�Ǝ����Ă݂Ăق����B�\�Z�s���̂��ߎ����Ă��Ȃ��AWE 755A�̑��ALancing Iconic���j�^�[�ARCA�̃��r�����X�E�V�X�e���A�O�H 2S-305�ȂǁA�����Z�p�̗��j��h��ւ������X�s�[�J�[������B�����������̃t�@���̑����́ASP�Ղ��܂߂��D�G�^���̃t�@���ł�����A�Âڂ������W�I�̓_���Ǝv���Ă��邩������Ȃ��B���������e���q�̊��m��Ȃ��͕̂s�����̂ł͂Ȃ����낤���H�@��͂胉�C�u�����̍čl���肢�����̂��B �y�T�u�E�V�X�e���ƕ���Ȃ���z �@�T�u�E�V�X�e���Ƃ͌����Ă��A��͂�I�[�f�B�I�E�}�j�A�̒[����A��Ƃ��ċÂ��������͎c�������B�ہA�T�u�E�V�X�e�������炱���A�X�s�[�J�[�E���j�b�g����A�����ȃg�����X�Ɏ���܂ŁA�����炵���咣�������Ƃ�����Ǝv���B����̃G���{�C�AUTC���g�����X�ALissen�Ѓ��W�I�g�����X�A����������������p�[�c����ł���A�g�ݍ��킹�Ɏ��s���Ă����������Ȃ����A���ۂɕs����ȕ����������Ă���B�������T�u�E�V�X�e�������炱���A�����ĉ������O���A�v��������`�������Ă݂邱�Ƃ��\�Ȃ̂ł���B���̏ꍇ�A�T�u�E�V�X�e���͖~�͂̂悤�Ȋ��o�ł݂Ă���B�����Ă����Ύ�����TPO�ɏ]����������̂ŁA�L�������l�߂���Ə�����������邱�Ƃʼn��P���Ă������Ƃ����l�������B�������V�������}�X�^�[�����̍w���ɂ��e�R���ꂵ�������Ă���Ƃ����̂����ۂŁA�Ȃ��Ȃ��C�s�̐g����E������Ȃ��ł���B �@���������i���̓���҂���݂āA���m�������Ƃ������������ɃC�W��₷�����A���Ȃ��Ƃ��A�r���e�[�W�E�p�[�c�ł́A�X�e���I�ő�����ƂQ�{�̂͂����A�R�{�ȏ�����̂��ƊE�̏펯�ł���B����قǃy�A�E�}�b�`���O�Ƃ������Ƃ�����B�X�e���I�Ƃ́A�{�����������@�ׂȂƂ��낪����A���ł��X�e���I�Z�b�g�ōw�����邱�ƂɊ����ƁA���o����Ⴢ��Ă���悤���B�r���e�[�W�X�ɍs�����Ƃ��ɂ́A�X���ɒĂ��Ȃ����̂ł��A�C�y�Ƀ��m�����p�̏o���ɂ��ĕ����Ă݂�Ƃ�����������Ȃ��B�X��Ȃ�Ɏv���t�������̂́A����Ȃ�̕i�ŃX�e���I�E�y�A�ɂȂ�Ȃ��������i�����A�荠�Ȓl�i�ŕ����Ă��炦�邱�Ƃ������B�����āA�����@�ނɂ��ď��k����Ƃ��ɂ́A�@�ނ����C�V�����邽�߂̃{�[�J�����ɉ����A�Y�݂̐[��CD�����������čs�����Ƃɂ��Ă���B�V�X�e����]�����邽�߂ɂ͌����Ȃ����̂�����ǁA�����A����œX��ɂ́A���̓Ǝ��̃T�E���h�n�D���Ă��炦�邵�A�������Ȃ�̍l�����Ԃ��Ă��邱�Ƃ������̂ŎQ�l�ɂȂ�B�Q�l�ɂȂ�Ƃ������x�Ȃ̂́A�قƂ�ǂ̓X��Hi-Fi�V�X�e�����Ă���̂ł����āA�J�}�{�R�������D�݂̐l������Ƃ����F�������Ȃ����߁B�ϋɓI�ɂ��ꂪ�ǂ��Ƃ������ߕ������݂��ɂł��Ȃ��̂�����ł���B �@��������č݂荇�킹�̃p�[�c�ō\�z�����T�u�E�V�X�e���́A���͎����̌����������݂����̂ŁA�N�����ƌ������Ǝ����D�݂̃T�E���h�ɂȂ��Ă���B���m�����~Low-Fi�����W�I���̉��A����͕��ʂ̃I�[�f�B�I�X�ł͐i��Ŕ����Ă������̂ł͂Ȃ��B�G���{�C��UTC���g�����X�́A�ʁX�̓X�ōw���������A���ǂ͓��{�ł͌ڂ݂��Ȃ��C�[�X�g�E�R�[�X�g�E�T�E���h�A������PA�@�ނ̂���ł���ƋC�t�����̂́A�w�����Ă��琏���ƌ�̂��Ƃł���B �@�ȉ��Ɏ��̃T�u�E�V�X�e���̍\���������B  �@������݂�ƌ��\�Ȑ��̋@�ނ�����悤�Ɍ����邩������Ȃ����A������CD�v���C���[�A�~�L�T�[�A�A���v�A�X�s�[�J�[�̂S�ŁA��Ԃ������|�����Ă�̂��X�s�[�J�[�ŁA���ɃA���v�ACD�ƃ~�L�T�[�͗]�蕨�őΏ�����Ώ\���ł���B�A���v�Ƀg�[���R���g���[��������A���m�����������������Ȃ��Ƃ����̂ł���A����ɃV���v���ȃV�X�e���ɂȂ邪�A�g�[���R���g���[���t�ŃA���v�̑I��͈͂��i����͈����~�L�T�[��t�����ق����֗��ł���B���̃~�L�T�[�ɂ�����������悤�ŁA�������߂ƒ�]����DJ�~�L�T�[ RANE MP2016���q���Ă݂���A�����ɑ��������ɂȂ�R���Ă��܂����B�����A�ԂɊ��܂��Ă���g�����X��^��ǃA���v�ƂԂ������̂��낤���A�������Behringer�̌��߂̉��̂ق����ǂ��悤���B�X�g���[�g���s���A�Ƃ���1990�N��̔��z���甲���o���āA�����鏊�ɓd�C�I�ȃg���b�v�����܂��Ď����D�݂̃g�[���Ɏd�グ�悤�B �@����ŁA���炭�g���E�}�̑Ώۂ������A�����Q���x���N�^ACO�̃��C�u�^���i1940�N��A�Z�e�[�g�^���j�́AFM�����̂悤�Ɉ��肵���T�E���h�Ŗ炷���Ƃ��ł��邵�A�r�[�g���Y��BBC�Z�b�V�����i1960�N��̃��m�����j���A1920�N��̉p�������W�I�p�g�����X�����܂��ĕ����Ƃ����r�Z�ŁAEMI�̂���Ǝ����V���L�[�Ń��b�`�ȉ���������Ƃ����A�~���N���ȑ̌�������i�̂�Pultec�^�C�R���C�U�[�ɂ����̗��Z�͂���j�B����������W�I�p�̎��^���������A���m��������̃��W�I������^���Ɏ��g��Œ����Ƃ������Ƃ́A�c�O�Ȃ���قƂ�Ǖ����Ȃ��B�������A�����̍D�݂ɐ����ɂȂ��ăT�u�E�V�X�e�����\�z����ƁA���ǂ͂����Ȃ����B�P�K�̌����Ƃ������ׂ��ŁA�T�u�E�V�X�e���炵���V�т��ł����Ǝv���Ă���B �@�Ƃ������ƂŁA�T�u�E�V�X�e���̈ꌏ�͂���ŗǂ��Ƃ��悤�B �y�Ȃ�ł����m�����z �@���m�����M�ɕ�������Ă���ƁA�N��������Ă݂����̂��A�X�e���I�^���̃��m�������ł���B�قƂ�ǂ̓r���e�[�W�@��őg���m�����E�V�X�e���̉����C�ɓ����Ă�����̂́A�X�e���I�^���̎��Y���̂Ă������Ƃ������́B������P�Ȃ�V���[�g��������A�g�����X�����ȂǐF�X���邪�A���̓~�L�T�[��Ńp���E�~�b�N�X���Ă���B�^���ɂ���ă~�b�N�X����ł���ق����Z�ʂ������Ǝv�����炾�B �@��ʂɃX�e���I���������m����������Ƃ��ɂ́A�ȉ��̂悤�Ȗ�肪�N����B �@�G�R�[�����͋t���̂��߁A���������邾�����Ƌ�����ł����������B �A�ł������ꂽ�G�R�[�����͍���ɏW�����Ă���A�J�}�{�R�^�̋l�܂������ɂȂ�B �c�܂�A�X�e���I������P���ɍ������킹��ƁA�����������ċl�܂�����������B���̂��߃��m�����ƃX�e���I�͌����̒��ƂȂ�A�ǂ��炩�Ƃ����ƃ��m�����͈������Ƃ������b�e�����������Ă���B �@�ŋ߂ɂȂ��ĊJ�Ⴕ���̂́A�ӂ��̉������~�b�N�X����ۂ� �@���`�����l���̃p���E�~�b�N�X�ʒu�𒆉��ɍ��킹��i���E�̉���������j �A�ǂ��炩�̃`�����l���̓��̓��x����6dB�グ��i�t���̃G�R�[�����������Ȃ��j �B�D�݂ɂ��ア���̃`�����l���̍�����{2dB���x�グ��i�v���[���X�̒����j 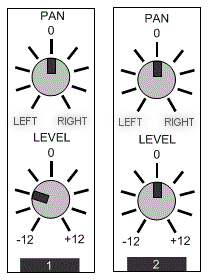 �c�Ƃ����菇�ނƂقƂ�ǂ̃X�e���I�^�����A���m���������Ă��N�x�𗎂Ƃ��������邱�Ƃ����������B�������ǂ��炩�̃`�����l������̂ɒ����Ă��邱�Ƃ͊m�������A�����Ă݂Ȃ��Ɣ���Ȃ����x�B����̕��͋C�ł͍��`�����l����傫�߂ɂ���Ƃ܂Ƃ܂�B �c�Ƃ����菇�ނƂقƂ�ǂ̃X�e���I�^�����A���m���������Ă��N�x�𗎂Ƃ��������邱�Ƃ����������B�������ǂ��炩�̃`�����l������̂ɒ����Ă��邱�Ƃ͊m�������A�����Ă݂Ȃ��Ɣ���Ȃ����x�B����̕��͋C�ł͍��`�����l����傫�߂ɂ���Ƃ܂Ƃ܂�B�@�v���[���X�̒����́A���E�ϓ����Ɖ��ڂ̃}�C�N�ʒu�ɕ������邽�߁A�����߂��ʼn��t���Ă���悤�ɂ������ꍇ�͎キ�����`�����l���̍��������߂ɂ���B�M�^�[�\���Ȃǂ́A��������ƃG�R�[��������܂蒼�ډ��̐c���o�Ă���B�t�Ƀ{�[�J�����́A���Ƃ��ƃ{�[�J���������߂��Ń��m�����^�肵�ăv���[���X���������Ă���̂ŁA��������߂�Ɣ�����ȉ��ɂȂ�B���b�N�̃��C�u�^���́A�t�ɃC���X�g�̐������o�����߂ɍ�����V�t�g����A���X�̒������\�ł���B �@�ʔ����̂̓X�e���I�^����CD�̓��m�����ɔ�ׂقڔ����̉��ʂł��邱�ƁB���m�����͑S�Ă̊y�킪������1������2�`�����l���������Ă��邪�A�X�e���I�͊y��z�u�U����2�����ɕ�������Ă��邽�ߍ������Ă��ق�1�������̏o�͂ɂȂ��Ă���Ɛ��������B���̏ꍇ�́A�A�i���O�̃R���v���b�T�[�����܂��Ă���̂ŁA���ʂ̃V�X�e���ɔ�ߓ��̘͂c�݂ɑ��鋖�e�͂��傫����������Ȃ��B���܂肱�̃��x�����͋C�ɂȂ�Ȃ��B �@���m������^�����I�[�f�B�I��]�Ƃɍ]��O�Y��������B�]�쎁�̂����͊��S�ɕЃ`�����l���݂̂ōĐ�����̂��ǂ��Ƃ������́B�Ƃ��낪�����̃r�[�g���Y�Ȃǂ̂悤�ȃf���I�E���m�����Ƃ����X�e���I�^���́A�Е��ɃM�^�[�A�Е��ɃX�g�����O�X�Ƃ����ӂ��ɁA���������S�ɍ��E�ɕ��������̂����邽�߁A�]�쎁�̂�����NG�B��L�̕��@�ŁA�����Е��ɃV�t�g���邱�Ƃłقږ��\�ɂȂ�Ǝv����B �@���߂Ċ��S�����̂́A�r���e�[�W�E���j�b�g�̉������̗ǂ��ƁA���m�����Ȃ�ł͂̍��i�̗ǂ����A�I���������Ă��邱�Ƃł���B����Ƒш�̋����r���e�[�W�E���j�b�g�́A�X�e���I���Ɨ]�C�����~�߂���Ėʔ��݂���������̂ɑ��A���m�����ɍi�邱�ƂŌ��_������Ă���B�C�ɓ������r���e�[�W�E�T�E���h�����炱���A�v�����ă��m�����ɃV�F�C�v�A�b�v����ׂ��ł���B �@����70�N��|�b�v�X�ł́A�����ʂł����̗����オ�肪�s�q�ŁA�h�����̃��Y�����s�V�b�ƌ��܂�̂ɁA�{�[�J����M�^�[�͂����Ɨ����Ƃ������z�I�ȏ�ԂɂȂ�B�Ⴆ�N�B�[���́u�O���C�e�X�g�E�q�b�c�v���Ă݂悤�B���̃A���o���͘^���N��ɂ���ă~�b�N�X�E�o�����X���傫���u����A���ꂪ�y�Ȃ̖��͂������o���Ă���̂����A�Đ������炷��Ƃ��Ȃ�̓�ւ������B��������m�����E�~�b�N�X����Ɖ��y�̍��i���������炯�o����A�e�^���̃��x�������ڗ������A���߂Ă��������Ȃ������̂��Ȃ��A�Ɗ��S���邱�ƂЂƂ����B �@�P�C�g�E�u�b�V���́u������v���A�ޏ��̃{�[�J�����|�b�J����G�̂悤�ɕ����яオ��A��w�~�X�e���A�X�ɋ����B�����ăP�C�g���j���A��Ȃ�A�����W�ł͂Ȃ��A�{�[�J���܂���܂ł����̂����悤�₭�����ł����B�Ƃ�������i�ƈ�̉������p�t�H�[�}���X���▭�Ȃ̂ł���B�������X�e���I�̂ق����g�ʔ����h�̂����A�ޏ��̓��̂Ȃ��ŕ`����Ă���X�g�[���[�́A���m�����ɂ��Ă����Ȃ�N���Ɏc���Ă���B�ނ���X�e���I�ł͒[�����ɒu���Ă���e�����������₷���Ȃ�A�V�i���I�{��Ў�ɂ����悤�Ȑ������ꂽ����������B����ł��������ꂽ�������ۂ����Ă���̂��A�ޏ��̐����Ƃ���ł���B �@���ƌ��\�ʔ����̂��N���t�g���[�N�u���˔\�iRADIO ACTIVITY�j�v�B����͉��Ƃ��Ē����̂ł͂Ȃ��A�I�[�f�B�I�@������̖�I�u�W�F�Ƃ��čl���锭�z�̓]�����V�N���B���m�����Œ����ĉ��߂Ėʔ����������ł����B���ہA���̍�i�͕��˔\�ƃ��W�I�����������Ă���̂��B �@�l���Ă݂�A���W�I�ł̃q�b�g�E�`���[�g���d�v������1970�N��̘^���ł���A���m�����ł����͂��`���悤�ȕi���Ǘ����܂��c���Ă����Ǝv���B�����g�͂��̔N��̗m�y���A�e�d�l�i�`�l���W�I�j�ƃx�X�g�q�b�g�t�r�`�i�e���r�j�Ŏ������Ă����̂ŁA�t������琂��傢�ɂ���Ǝv�����A���߂Ă��̍��̊��o�͂��ꂾ�����̂��Ǝv���B�܂�y�Ȃ��ƂɃX�e���I�̒����Ƃ������Ƃɓ����g�킸�A�y�Ȃ̈�ۂ�h�Â��݂Œ��������Ă������Ԃ��A�悤�₭���߂����̂��B �@�N���V�b�N�ł́A60�N�㏉���܂ł̃X�e���I�^�����������ǂ������ł���B���Ƃ��ƃ��m�����Ղƕ��s���Ĕ̔����Ă��������̘^���ł�����A���̌G��肪�ǍD�ł���B�R�����r�A�AEMI�ARCA�ȂǁA�Y�����̃}�G�X�g�����������ɂ܂������Ę^�����Ă���B�����̓X�e���I�𐳋K�Ƃ��邪�A�Ⴆ�P���v�̂悤�ɉ��t�X�^�C����ς��Ă��܂����l�ɂ��ẮA�ǂ�����M�d�ȉ��t�L�^���Ǝv�����A���҂��ɕ]���ł���V�X�e���̍\�z�͑���B�ŋ߂ɂȂ��āA�����̘^���������ő�ʂɃZ�b�g�̔������悤�ɂȂ������A���m�����ƃX�e���I�������፬���ɂȂ��āA�ǂ������ėǂ��������Ă��܂��i���Ȃ��ґ�ȔY�݁j���A�Ƃ肠��������Ⳃ�����ꂽ�����B���ƁA���̍��̎����y��[�g�̘^���ɂ́A�\���X�g�����Ɋ���Ă���^���������i�Ⴆ�V�F�����O�^���[�r���V���^�C���̃u���[���XVn�\�i�^�W�Ƃ��j���A�����������̕Ћ��ŋ��������ɕ�������̂���ł���B�������������m���������邱�Ƃŕ����₷���Ȃ�B�V�F�����O�̃u���[���X�́A�S�[���h�x���N�̕ăf�b�J�^���ȂǂƔ�ׂ�ƁA���҂Ƃ��Ƀt���b�V���剺�̔�����L���ɔ��������t�Ƃł��邱�Ƃ�����BBBC��1959�N�ɃX�e���I���^�����z�[�����V���^�C���w���́u��l�̌����ȁv�́ABBC�̃u�������C�����������m�����ւ̉��ʌ݊������ǂ��Ǝv����_�ƁA���E���A���o�����X�Ƀ~�b�N�X���邱�ƂŁA���̉��ߊ�����������A�L���z�[���̂Ȃ��ʼn������Y���l�q�������ɔ���B �@�ӊO�ɑ������ǂ��Ǝv����̂��A�Êy��̘^���ŁA�ߐڃ}�C�N�Ř^�邱�Ƃ̑������ƁA�C�R���C�U�[�̃f�t�H�������ɗ͔����Ă��邽�߁A���̂܂܍Đ�����Ǝ�����̉��ʂłȂ��Ƃ��ׂ����ɂȂ�₷���B�r���e�[�W���j�b�g�́A���ꎩ�̂ɃC�R���C�W���O������Ă��邽�߁A���������^�����₷���A�Ƃ�����胊�A���ɍČ��ł���B���N�̃��q�^�[�Ȃǂ̉��t�ƕ�����ׂĂ݂�ƁA���t�Ƃ̃p�b�V�����������y�U�ŕ]���ł���B�������i���l�����ő�Ȃ��Ƃ��Ǝv���B �@�W���Y�͍��ł����m�����h���������ɂ́A�ӊO�ɃX�e���I�E�Z�b�g�Ŏ������Ă���l�������̂ł͂Ȃ����낤���B��������������_���E�W���Y�Ƃ����W���������A1960�N��ň�x�r��邱�Ƃ��l����A�����ă��m���������ŕ����ʂ����Ƃ��\�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���H�@���m�����ł���������g�p����̂́A�f��ق̂悤�ȍL����Ԃł̂��Ƃł���A���{�̈�ʓI�ȉƉ��ł̓X�C���O�ł��鉹�ʂ̊W�����܂��ĂP�䂪�����I�Ȃ̂��B���Ƀr���e�[�W�@�����J���ď�肱�Ȃ��Ă���l�ɂ́A�y�A�̂ǂ��炩���̏�Ƃ����J���ڂɍ������ꍇ�̕��ւƂ��Ĉ�x�����Ă݂ė~�����Ǝv���B �@���������X�e���I���Ƃ����͉̂��t�̖��͂�`�����v�f�ł����āA�_�C�i�~�b�N�ȉ��y�̊�{�v�f�̓��m�����ł��\���`���B���ۂɁA�A�R�[�X�e�B�b�N�y��ł������艉�t�����ŋ߂̃N���u�E�~���[�W�b�N�iECHOSYSTEMS�Ƃ����k�����j�b�g�j���A5kHz���猸������Â��g�����X�Ńt�B���^�����O���ĕ����ƁA�O���[�u�̖{�����͋������ł��Ă���B���́A�N���u�n�E�X�̉����͂₽��ɍ�������������킯�ł��Ȃ��A�����̐l�̓O���[�u�ɏ��邩���Ȃ����A�Ƃ������Y���̍��i�����Ŕ��f���Ă���̂ł���B�����Ă��ꂪ�I������ƁA����܂ł̃I�V�����n�̃��e�����y���A�ُ�ɃX�s�[�h���̂��钴��h�����̉��y�ɕς��B������ꂪ���̘^���̖��͂̑S�Ăł͂Ȃ��B�������~���[�W�V�����̐����͈��|�I��Low-Fi�����m�����̏����ł���B �@�L�[�X�E�W�����b�g�́u�P�����E�R���T�[�g�v�����āA�ǓƂƘa���Ɏ��陋�߂��̖{���͉���ς��Ȃ����肩�A���m���[�O�Ƃ��Ă̐��݂��X�g���[�g�ɓ`���B1950�N��̃P���v�̒e���x�[�g�[���F���E�\�i�^�Ɣ�r���Ă��A�O��I�ȌǓƂ��琶�ݏo�����s�A�m���y�̖{�������Ɏ��ʂ��Ă��邱�Ƃ�����B�����ăX�e���I�����������Ƃ����ƂŁA���m�N���ʐ^�̂悤�ɑΏۂ��N���[�Y�A�b�v�������ʂ�����̂��B�s���g�������{�P�Ă�����A�t�B�����̗��q�̑e���������Ă��A�A�e�����Ŕ�����̋�����������A����ŏ\���ɉ��荇����B �@���ƈ��z���u�X�̐��E�v��5kHz��Low-Fi�g�����X�ŗ��Ƃ��đS�����Ȃ��B��������70�N��̉��y�i�����̈��r�Ȋ������o�Ă��Ėʔ����B���̎���̓g���G�E���A�A�r��R���A�O���V�F���E�X�T�[�i�ȂǍD���ȉ̎肪�����̂ŁA��ꐺ�����������u�Ԃ���Ȃ�ƂȂ��z�����Ƃ��Ă��܂��B�_�炩���s���g�̍��������m�N���ʐ^�̂悤�ɁA���̗͂]�v�ȃ��m����菜�����悤�ȁA����ł��ēd�Ԃ̃K���X�z���ɒ��߂Ă���悤�ȁA�s�v�c�Ȏ��Ԃ�����Ă���B �@�u�Ȃ�ł��X�e���I�v�ŕ������Ƃ����̂́A���̔ėp���Ƃ͗����ɁA�X�s�[�J�[�̂��T�E���h�E�X�e�[�W�̕ȂƂ����ʂ̗v�f�������A�������ɂȂ������������ŁA�ӊO�ƒ��f�ȗ��ꂪ�ۂĂȂ��̂�����ł���B�^����ԂŁu�H�v�Ǝv�����Ƃ�����A���m�����Ŏ������Ȃ����Ă݂�ƁA���i���͂����肵�āA���t�{���̔�r�����₷���Ȃ�̂͊m�����B �y�l�b�g�Љ�̃��m���������z �@�I�[�f�B�I�D���̐l�́A�Ƃ������W�I��ډ�����B�u���W�I�݂����ȉ��v�Ƃ����ƁA���̑��u���J�}�{�R�^�̉��Ŕ�Hi-Fi�I�Ƃ����B��ł���B�����ĒN�ł��^�_�ŕ����邩��Ƃ������R�ŁA�킴�킴�������o�����l�̂Ȃ����́������Ƃ������b�e��������B�Ƃ��낪���m���������ƌ��������Ƃ��ɂ́A�K������AM�����̉����ш�F80Hz�`8kHz�Ɗi��������Ȃ��B�Ƃ������A���̑ш���ǂ������o�����X�ł܂Ƃ߂邩�A�Ƃ������Ƃ̓I�[�f�B�I���u�̊�{�ł���悤�Ɏv���B�l�̐������R�ɕ������邱�ƁA����̓X�s�[�J�[�����܂ꂽ�Ƃ�����ۂ���ꂽ�������ł���B �@�������A���̑ш�ւ̈����Ƃ��������O�Ƃ����ׂ����̂́AFM�X�e���I��������ʉ�����1970�N�ォ��傫����ނ��āA���ꂱ��40�N�ȏ���߂������āA���Ə����Ŕ����I�o���ƂɂȂ�B���͂��̊Ԃ̃e���r�ł̃��m���������̎��̌�ނ��������̂��B����������A�l�̐�����������ނ����Ƃ������悤�B�K���E�}�C�N��x���A�E�}�C�N�𑽗p���邱�ƂŁA���͂̉����ɒ[�Ƀt�B���^�����O������^�����S�ɂȂ�A�����K����S/N��Ƃ��s�[�N���x���Ƃ����\�ʓI�Ȃ��̂ŊǗ����ꂽ���ʂƂ�����B����̃o���G�e�B�[�Ō|�l�������̂��A�����ʔ��������ł͂Ȃ��A���C�u���Œb�������̗}�g���������肵�Ă��邩�炾���A��̎B�e���K�v�Ȃ��R�}�[�V������A�j���̂ق����A�����Ƃ����^���u�[�X�Ƒ�^�}�C�N�Ŏ��^���Ă��镪�A���̍��i���������肵�Ă��邩������Ȃ��B�h�L�������^���[�̃A�i�E���X�̐����A�f���������ꐫ��������ł���悤�Ō��\�D���ł���B���̓_�Ń��W�I�́A�̂Ȃ����^�_�C���t�����̃}�C�N���g���Ă̂P�{�����E�E�E�Ǝv���Ă�����AAM�ǂł͍ŋ�AKG�Ђ̃O�[�X�l�b�N�E�}�C�N���g�����Ƃ������悤�ŁArajiko�Ȃǂ̃C���^�[�l�b�g�E���W�I�Ŋm�F���Ă݂�ƁA���^�}�C�N�炵���J�b�`�����������Ōł߂Ă���BFM�ǂ̂ق������̐������ӎ����Ă��A��^�_�C���t������{�[�J���}�C�N���g�p���邱�Ƃ������悤���B������^�_�C���t�����Ńp�[�\�i���e�B���߂Â��߂��āA�ߐڌ��ʂŋ���������Ė��ēx�𗎂Ƃ��Ă��邱�Ƃ�����A�����������Ƃ͏��^�O�[�X�l�b�N�ł͋N����Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��������^�̃v�����ꏏ�Ȃ̂ŁA����������邱�ƂŁA���g���݂̂��鐺��_�����Ƃ����邩������Ȃ��B������ɂ��Ă��A�����W�������Ǝv����r���e�[�W�̃t�������W�ł��A���������Ⴂ�����R�ɕ������邱�Ƃ��l����ƁA�l�̐����Đ�����\�͂Ɋւ��ẮA50�N�O���炻��قǐi�W���Ȃ��ǂ��납�A�ނ����ނ��Ă�����̂������悤�Ɋ�����B
 �@�ʔ����̂́AHi-Fi�̗��j�ɖ����c�����X�s�[�J�[AR-3�̊J���҃w�����[�E�N���X���A�ӔN�ɔ��\����Tivoli Audio�Ђ�Model
One���B�G�A�T�X�y���V���������̖��^�u�b�N�V�F���t�ɗ��܂炸�A�h���r�[B�^�m�C�Y���_�N�V�������ŏ��Ɏ��������J�Z�b�g�f�b�L�A�v���W�F�N�V����TV�̊J���ȂǁA�����Ŏ�y�ɍ��i���Ƃ��������^��AV�@��̐�[�𑖂��Ă����N���X���̏I���_���A���m�����E���W�I�ł������_�͔��ɋ����[���B���W�I�̎��͂Ƃ��ẮA�\�j�[��ICF-EX5�قǂ̐�ΓI�ȐM���i������AM�����ɓq�������O�͔��[�ł͂Ȃ��j�͂Ȃ����A�����@��Ƃ��Ẵ��m���������̕i���ɒ��ڂ������Ǝ��̂��T�v���C�Y�ł���B���ɐ��̃I�[�f�B�I�̗��j���̂��̂�̌������l�Ȃ�ł͂́A�[�����@�ɖ��������i�ł���B21���I�ɂ��Ȃ��āA�Ȃ����ǂ����W�I�H�A���������m�����ŁH�A��������Hi-Fi���_�̏펯���悤�ȋ^��Ƃ͗����ɁA���̉��ɂ͎q������V�l�܂Ŗ�����������͂�����B�t�����X�̎q�����g���p�̃A���e�i���Ȃ��ėǂ����Œ������Ƃ���l�q�Ƃ��A�x�e������TV�A�i�E���T�[�����W�I�̗��j�ƈꏏ�ɏЉ��̂�����ƁA���̃��W�I�̖��͂��[�����Ƃ�����B�������Ai-pod�̂ق����I�[�f�B�I�@��Ƃ��Ă̊v�V���͖��������AModel
One�̂悤�ȃA�i���O�@�킪����V���v���ȉ����Z�p���܂��A���ۋK���i���[���h�E�X�^���_�[�h�j�̐������p���Ǝv���B �@�ʔ����̂́AHi-Fi�̗��j�ɖ����c�����X�s�[�J�[AR-3�̊J���҃w�����[�E�N���X���A�ӔN�ɔ��\����Tivoli Audio�Ђ�Model
One���B�G�A�T�X�y���V���������̖��^�u�b�N�V�F���t�ɗ��܂炸�A�h���r�[B�^�m�C�Y���_�N�V�������ŏ��Ɏ��������J�Z�b�g�f�b�L�A�v���W�F�N�V����TV�̊J���ȂǁA�����Ŏ�y�ɍ��i���Ƃ��������^��AV�@��̐�[�𑖂��Ă����N���X���̏I���_���A���m�����E���W�I�ł������_�͔��ɋ����[���B���W�I�̎��͂Ƃ��ẮA�\�j�[��ICF-EX5�قǂ̐�ΓI�ȐM���i������AM�����ɓq�������O�͔��[�ł͂Ȃ��j�͂Ȃ����A�����@��Ƃ��Ẵ��m���������̕i���ɒ��ڂ������Ǝ��̂��T�v���C�Y�ł���B���ɐ��̃I�[�f�B�I�̗��j���̂��̂�̌������l�Ȃ�ł͂́A�[�����@�ɖ��������i�ł���B21���I�ɂ��Ȃ��āA�Ȃ����ǂ����W�I�H�A���������m�����ŁH�A��������Hi-Fi���_�̏펯���悤�ȋ^��Ƃ͗����ɁA���̉��ɂ͎q������V�l�܂Ŗ�����������͂�����B�t�����X�̎q�����g���p�̃A���e�i���Ȃ��ėǂ����Œ������Ƃ���l�q�Ƃ��A�x�e������TV�A�i�E���T�[�����W�I�̗��j�ƈꏏ�ɏЉ��̂�����ƁA���̃��W�I�̖��͂��[�����Ƃ�����B�������Ai-pod�̂ق����I�[�f�B�I�@��Ƃ��Ă̊v�V���͖��������AModel
One�̂悤�ȃA�i���O�@�킪����V���v���ȉ����Z�p���܂��A���ۋK���i���[���h�E�X�^���_�[�h�j�̐������p���Ǝv���B�@���������A�i���O����̉����Z�p�̕����́A���R�Ȃ���MP3�ɑ�\����鈳�k�����Z�p�̑䓪�ł���A���Ȃ��_�C�i�~�b�N�����W�Ŕ@���Ɍ��ʓI�ɉ�����`�B�ł��邩�A�Ƃ����ۑ肻�̂��̂�1930�N��̃L�[���[�h���Ƃ������Ƃ�����B���̂Ȃ��Ńt�������W�̖��͂ɋC�t�����l���������̂́A�l�I�ɂ͑劽�}�ł���B �@����Ń��B���e�[�W�ȃt�������W�����āA�l�b�g���W�I�̂悤�Ȓቹ���ւ̑ϐ��͔��ɋ����BMP3�͍����̃r�b�g����[�܂邽�߂ɁAHi-Fi�̗��V����O��Ă���A�_�C�i�~�b�N�����W���������ł���ȂǁA�]���̃A�i���O�Z�p���t�����銴���ɉ]����B�������Ȃ���A1950�N��̗L���Z�p�́A��km�̐ڑ��P�[�u���Œ����Ă���悤�Ȃ��̂ŁA���̗����������������������B���C�u����PA�Ȃǂ͂܂��ɁA�����W�𐧌����Ȃ���{�����[������^����Z�p���̂��̂ł���B�����̏��L���Ă���G���{�C��SP8B�Ȃǂ́A��������Hi-Fi��Low-Fi�̂ǂ�����Đ����邽�߂̋���̍����Ă���A�l�b�g���W�I�����\�ʔ����������Ă����B���b�N��70�N�オ���S�ŃI�[���f�B�[�Y���قƂ�ǂ��Ȃ��̂œ���̂����A�X���[�X�E�W���X�Ȃǂ͐V�����킸���B���e�[�W�@��̓ƒf��ł���B�����ĈӊO�Ȃ̂́A�ŋ߂̌Êy��ʼn��t���ꂽ�o���b�N���y�ŁA���B���e�[�W�E�I�[�f�B�I����ԕs���ӂȕ���̂悤�Ɏv���Ă������A���m�����Œ����ĂȂ��ʔ����Ƃ����ӊO�Ȍ��ʂ������B �@���R�ɂ��čl���Ă݂�ƁA�ЂƂ͒�����ɖ��Đ�����������l�b�g���W�I�̖��t�����|�����Ă��ă��@�C�I�����Ȃǂ��Y��ɖ邱�ƁA���ɒ���̉����o���������r���e�[�W�E���j�b�g�ł͂��ꂪ���邳����Ȃ����ƁA����ƃX�s�[�J�[�̊y��̂悤�Ȍ����T�E���h�ɋ̒ʂ������ꊴ�������炵�Ă��邱�ƁB�Ō�̈�т����|���V�[�́A���̍������x�Đ����Ƙ^���i���̈Ⴂ���ڗ����₷���Ƃ�����A���܂����ς��ĉB���Ă���悤�Ȃ��̂ŁA�ӊO��UTC�̃g�����X�̃t�B���^�[�����O���������Ă���̂�������Ȃ��B���Ƃ��ƃG���{�C�́A1970�N��ɂ����Ă��}�C�}�C�N���A���v�Ɍq���Ŏ����̐��Ńo�����X��������Ɖ]���悤�ȃ��[�J�[�ł���B�����̑f���C�Ȃ����ł�����Ȃ�ɍĐ�����悤�ɂł��Ă���̂ł���B�����ƊE�̋���ׂ��`���Ƃ������̂��_�Ԍ����悤�ȋC������B �@�y�[�W�ŏ��� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||