

我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。「華麗なる古楽器の世界」はオーディオ再生で最も不得意な分野として、筆者の悪あがきの情況が綴られています。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)なぜかJBL+AltecのPA用スピーカーをモノラルで組んで悦には入ってます。 5)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華麗なる古楽器の世界
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事の始まり】 文化的背景 ルネサンス〜バロック音楽とは昔から音楽史と言われてきたように、ようするに文献上での音楽を演奏して観賞しようとする行為全般のことを差してるようです。大きな変化はロマンティークなアプローチで知られた19世紀の演奏スタイルから、ドイツを中心とした楽譜書いてあることのみで演奏する新即物主義、その反動か極左によるオーセンスティック(原点主義)な解釈からなるピリオド楽器(古楽器もという)による演奏という過程を経て、現在の古楽ブームという現象を形作られています。とはいえ個人的には、ルネサンスは9世紀のカロリング・ルネサンス以降に地道に積み上げられたアラブ〜グレコ・ローマン文化との交流と考えているので、中世音楽と呼ばれるロマネスクやゴシック期の音楽も含まれていると考えて欲しいと思ってます。 私の古楽経験は1980年代に高校のコーラス部に入って、ByrdやVictoriaのルネサンス・ポリフォニーを歌ったり、音楽の授業でA=415ピッチの木製リコーダーでアンサンブルを組んで、ジャヌカンの「鳥の歌」などを演奏したり(バス・リコーダー担当)で、極めて技巧的なバロック音楽には近づかなかったものの、ヨーロッパ古楽への思いは素地としてありました。大学でも3つの合唱団を梯子しながらモンテヴェルディ、パレストリーナ、タリス、ジョスカン、ラッススなどルネサンス音楽との付き合いは途切れることはなく、就職後はキリスト教会での讃美歌指導など様々な奉仕を通じて、自分もそこで音楽的なアプローチを模索しています。ちなみに自分の通ってる教会はコンクリート打ちっ放しの非常に響きの良い礼拝堂です。 そういうなかでルネサンス〜バロック音楽というジャンルをどう考えているか? というと、ひとつは機会音楽という一期一会の出会いのなかでのおもてなしの精神が気に入っています。当時の作曲家は自身が楽士として身を立てていたこともあり、楽譜に細かな指令を書いて他人に演奏してもらうということはあまり行わなかった。むしろ自分の腕だけで音楽を振る舞うという、極めて心身のバランスのとれた所作が音楽家としてのマナーだったように思います。もちろんそこには貴族社会というドメスティックな圧力があったにせよ、当時の楽士がもつ謙虚で情熱的なマナーには学ぶべき点が多いです。 もうひとつの気に入った点は、響きの強い礼拝堂でのアーティキュレーションを極めるのに様々なヒントが得られることです。とくに旋法のピッチに関する情報は、古楽奏者の録音は様々なものをもたらしてくれて有益です。讃美歌の場合、楽譜の伝達とは裏腹に本当に平均律が行き渡るのは19世紀後半になってからで、自分のなかでは讃美歌の旋法とピアノの調律が合わない(ようするにハーモニーの純正律だけではなく、メロディーが重なっても濁らないいくつかの工夫がある)と思うことは感覚的にはあったのですが、実際にそういうふうに歌っている人に巡り会うことは非常にまれです。しかし最近のいくつかの古楽演奏を聴くとそういう工夫が随所に感じられるのである。 再生機器
1)スピーカーの音調(トーン)を整える ピリオド楽器による最初のアプローチは鍵盤楽器から始まります。ドイツのルネサンス・オルガンおよびシュニットガー・オルガンを使ったヴァルヒャのバッハ・オルガン全集(1947−1952年)などはその最も早いものでした。60年代からようやくレプリカのチェンバロ製造が始まりレオンハルトによる演奏でほぼ決定的になります。バロック・バイオリン、ヴィオラ・ダ・ガンバ、トラヴェルソはクイケン兄弟、ビルスマ、ブリュッヘンなどのオランダの奏者がこぞって演奏しその地歩を固め、歌唱ではデラーのカウンター・テナーが最も衝撃的な出来事で、ジェンダーの差別もあって舞台活動そのものを奇異に評する人も耐えなかったものの、ルネ・ヤーコプスがバロック・オペラの上演で実績を上げるにしたがって、その意義も広く認知されるようになりました。 1970年代までの録音は、ほぼ例外なくノイマン社の大型ダイヤフラムのコンデンサー・マイクが用いられていて、ほぼフラットな特性のなかに中高域に幾分の輝きのあるキャラクターをもたせてあります。これは精度の良い金属箔を用いたダイヤフラムを2way化することによって高域を持ち上げているからで、深く伸びた低音と明瞭な高域が得られる反面、低域の回り込みによるブーミーな膨れあがりや、中高域でのカサカサした音などを過敏に拾う癖もあります。昔、この手のマイクの前で歌うときに「舌なめずりをするな」と注意を受けたことがあって、ペチャペチャと鳴る音域に極めて過敏に反応してしまうのようです。 そのことで何が問題なのかというと、ピリオド楽器のノイズ成分の扱いです。チェンバロを引っ掛ける音、バイオリンの弓が微妙にかすれる音、トラヴェルソの息音など、古楽器特有の原始的な魅力は非音楽的な要素として汚く収録されます。大型ダイヤフラム特有の輝く中高域の特長はそのまま欠点として、古楽器の魅力を半減させてしまうのです。最近は真空管マイクが増えてこの過度特性が緩和されているように思います。もうひとつは楽器間の明瞭度を確保するために、楽器の手前にマイクを立てるマルチマイクで収録することで近接効果による中低音の被りが感じられる録音も少なくないことです。オーディオ的にバランスを取ろうとして無理に中低音をふくよかにする必要などほとんどないし、バロックの粋である通奏低音の軽やかなパッセージにとってはマイナスに感じます。それにも関わらず、こういう録音は1980年代前半まで行われていたわけで、それだけ50年代から続いたHi-Fi再生でのオーソドックスなバランスが保守的に作用していたからだと思う。 こうしたマイク特性を考慮してニュートラルな音調に整えるには、以下の方法が有効です。ひとつは実際の収録音と再生音量とのバランスを保つためにラウドネス補正を掛けること、ふたつめはコンデンサー・マイクの近接効果をキャンセルして音調をスマートに収めることです。(このことに関する仔細なデータはAES研究部会のBruce Bartlett氏の論文参照) 以下の図から判ることは、一般にフラットが良いと思われてる特性ではプレゼンスが強すぎて中高域がうるさく、逆に8kHz以上のアンビエンス成分が薄く感じられ音がくぐもり、場合によってはスーパーツィーターを足すことでバランスを取ることも必要になります。この方法で調整すると、柔らかさと天上の抜けの両立が感じられ、アンサンブルの綾は絶妙になります。
2)楽器と会場のハーモニーを愛しむ ピリオド楽器と一口に言っても、かの時代の全てのジャンルを含んでます。映画評論家が外国映画ベストを投票しようという企画で、「フランス料理もあれば、中華やエスニックも混ぜこぜで」と皮肉ったことがありますが、これはバロック音楽の鑑賞にもまるまま当てはまります。小さなサロンもあれば大聖堂もあり、芝居小屋や野外での大道芸など、音楽を奏でる全てのシチュエーションを内包しているんです。それをひとつのスピーカーで奏でるというのだから、本当のところかなり無理な相談です。しかしスピーカーの奏でる最大公約数の音で楽器や演奏会場のテイストを味わうことはできるというのです。 最近の録音は大型コンデンサー・マイクの代わりに、B&K社をはじめとする無指向性マイクでのワンポイント収録が増えつつあります。小型ダイヤフラムの正確なピストン運動を伴いつつ近接効果やキャラクターを排除した測定用マイクで、最初はPCM録音のパイオニアであるDENONが取り上げて認知されるようにないました。無指向性マイクでの収録は音は素直だが、音像がぼやけた感じになりやすく、オーディオ的に低音の膨らみなどの魅力も乏しい。めじりがとぼけて肌は荒れ気味…いわゆる「すっぴん」の音です。 これがピリオド楽器にどうして有効なのかというと以下の利点があります。 ●千変万化するピリオド楽器の音色の変化が素直に楽しめる ●録音会場も楽器のうちだとすれば、その音響特性にも脚色を伴わない ●アンサンブルの微妙な綾が自然なバランスで再現される 一方で欠点は以下のようなものです。 ◆マイクの素地の音が出やすくそれが癖につながる ◆壁の輻射を全て拾うので良い会場でないと音像のピントがぼけやすくなる ◆いわゆるステレオ音場が会場の情況で不安定に変るので再生機器の癖が出やすい しかし良質なワンポイント録音は、古楽演奏に特有の繊細で情熱的な面を逃さず伝えてくれます。反対に楽器毎にマイクを立ててバランス調整して収録されたマルチマイク録音は、古楽器の音という一種の紋切り型のサウンドを奏でるようです。ワンポイント収録は演奏のシチュエーション全体を取り込んでしまうため、再生装置にキャラクターが残る場合には、録音方法ではなく現実の音響に対する得手不得手が鮮明になります。ピリオド楽器特有のノイズ、深いエコーまたはフラッター(龍鳴り)など、いままで楽音には含まれない要素が実は味のある音を醸し出していると言えます。和楽器には「さわり」というノイズ成分を楽しむことがありますが、リボンマイクがそうした過度特性を柔らかく収録して相性が良いといわれます。ピリオド楽器もそういう感じで録音できないものかと思う今日この頃です。 ページ最初へ 【お茶など飲みながら】  実はバロック音楽の鑑賞では本質的なことがあります。それは一種の貴族趣味を味わうことです。香り立つお茶など静かに楽しみながら聴くのがマナーともいえましょうか。とはいえトルコ風に寝そべって聴くのもよし、書斎で書き物を認めつつ聴くのもよし、機会音楽の味はどこまでも広がるように思います。 実はバロック音楽の鑑賞では本質的なことがあります。それは一種の貴族趣味を味わうことです。香り立つお茶など静かに楽しみながら聴くのがマナーともいえましょうか。とはいえトルコ風に寝そべって聴くのもよし、書斎で書き物を認めつつ聴くのもよし、機会音楽の味はどこまでも広がるように思います。しかしオーディオは家庭での調度品としての地位は既に得ているものの、そのデザインはあきらかにアール・デコ以来の機械文明礼賛の風潮があります。サイレント映画「メトロポリス」に観るように悲劇的な機械文明の奴隷としてアイデンティティの崩壊を伴いながら、不確かな未来を映し出す鏡のような存在でもあります。それが今のオーディオ機器の金ピカ&成金デザインを流行らす結果になっているのか? よく判りません。 富士通テンのEclipseシリーズはエッグ・シェル(卵の殻)の形状をしています。70年代のスペース・エイジを連想させるデザインですが、自分ではオーガニック・デザインの一種だと思っています。一方でピリオド楽器の材料は自然のものしか用いておらず、いわゆるスロー・ライフを地で行っているようなものです。モダン・アジアンなどのインテリアが合わないだろうか…中国茶など飲みながらゆっくり考えてみたいものです。タイのオーディオメーカーにnOrhというのがありますが、太鼓のような奇抜なデザインながら気負いなくアジアン家具なかで調和しています。(1,2,3) 東南アジアのインテリアは独自の伝統意匠とバロック時代のスペイン、オランダなどのテイストが微妙に混じり合っているようです。 少し前までは伝統文化に対する混血文化のように評されていた植民地文化ですが、現在のような民族・宗教紛争の絶えない情況のなかでは、むしろ穏やかに文化が生きのびていく手本のように考えられます。バロック音楽の演奏方法もオーセンスティック(原典主義)という価値観から、アラブやシルクロードなどの広い影響のなかで歴史観を形成しつつあり(例えばザイードのオリエント観やバルトルシャティスの印章学のように)、そういうなかで民族音楽の伝承者たちと古楽器奏者の位置関係について、より親密な交流が成り立つのではないかと考えられます。 現代の楽士たちのもてなしに身を委ね、東洋からヨーロッパに広がった嗜好品である茶を傾けながら、バロックのもうひとつの核であるアジアの視点を考えるのもまた一興でしょう。 ページ最初へ 【バロック・バイオリン格闘術】  ともかくバロック社会は完全なる身分と秩序の社会である。楽士は名誉でも汚されようものなら弓を研ぎ澄まし、トーナメントで相手を斬り倒してでも生き残らなければならない。。。というのは冗談として、こと昨今のバロック・バイオリンの奏者に関していえば、そういうエキセントリックな雰囲気が漂います。知的なオランダ勢(クイケン、寺神戸など)、熱血漢のイタリア勢(ビオンディ、オノフリなど)、手堅いイギリス勢(スタンデイジ、R.ブラウンなど)、それぞれの流派が自分たちの奥義を展開する華々しい世界です。モダン・バイオリンではクライスラーの出現以来、アウアー派vsフランコ=ベルギー派の派閥争いは無くなって久しいというのに、今時分、バイオリンの流派でこれほど競い合うというのも珍しいと言うほかない。そういうバロック時代に存在した競争原理をも再現しているようにも感じられます。 ともかくバロック社会は完全なる身分と秩序の社会である。楽士は名誉でも汚されようものなら弓を研ぎ澄まし、トーナメントで相手を斬り倒してでも生き残らなければならない。。。というのは冗談として、こと昨今のバロック・バイオリンの奏者に関していえば、そういうエキセントリックな雰囲気が漂います。知的なオランダ勢(クイケン、寺神戸など)、熱血漢のイタリア勢(ビオンディ、オノフリなど)、手堅いイギリス勢(スタンデイジ、R.ブラウンなど)、それぞれの流派が自分たちの奥義を展開する華々しい世界です。モダン・バイオリンではクライスラーの出現以来、アウアー派vsフランコ=ベルギー派の派閥争いは無くなって久しいというのに、今時分、バイオリンの流派でこれほど競い合うというのも珍しいと言うほかない。そういうバロック時代に存在した競争原理をも再現しているようにも感じられます。これだけ華麗でありながら競争の激しい世界です。オーディオ再生で困らないというのは嘘です。ハタから観戦するトーナメントは面白いが、ノコギリで斬りつけるような音が耳元で…と思ったら最後。絶え間なく殺伐とした時間があなたの神経を逆撫ですることでしょう。これを防ぐにはどうしたらいいのか? 肥え太ったオーディオ装置のダイエット作戦の開始です。まずスピーカーの設置を疑うこと。柔らかい地の緩衝剤などはまず外さなければなりません。これは反対のようだが、耳障りになる原因が高域の共振(リンギング)に由来しているので、スピーカーの固定がぶれると振幅の小さい中高域では共振(リンギング)を招くことになる。低域が肥って聞こえる一方で高域が細身に感じるときも、これに由来しているようです。低音の豊かなピラミッド・バランスはクラシックの基本のように云われてきましたが、通奏低音などにパッセージが混み合う古楽の録音ではむしろ好ましくないと思います。なのでダイエットする方向にします。次にアンプのケーブル類の点検です。ここで気を付けなければならないのは、ただ音が柔らかくなるだけではバロック・バイオリンの狂気をスポイルしてしまうので、音の勢いを失わずにチューニングするのが狙い目です。私はケーブルを最初はストレートな音のするもの、端部に柔らかい音のするものを50cmほど短く継ぎ足して使っています。情報量は単純に全体の長さで決まりますが、どういうわけかトーンは最後の接続点で決まるようです。 それなりにダイエットが成功したら、もう一度ほかのソースも流してみましょう。するとバロック奏者の誰もが踊ることをこよなく愛していることに気付くはず。武闘は舞踏派の間違いだったわけ。さて、バロック・バイオリンの華麗なるトーナメントを存分に楽しみませ。 ページ最初へ 【人の声?天使の声?】  この時代はともかく凝った宗教曲が多い。19世紀のように寄せ集めの市民合唱団など目ではない。専門の聖歌隊が聖職者の地位にしっかり食いついていました。しかしいちど失われた聖職禄を礼拝堂のなかで再現するのは並大抵のことではありません。由緒あるほとんどの聖堂は数百年かけて接ぎ木のように増築されていますので、全体に良く響くものの、どの場所で歌うのが効果的か? 聖書朗読などナレーションに向いた位置はどこか? など、およそ一般のコンサート・ホールのように決まった法則というものがない。聖餐の盃を掲げる場所に適した場所が必ずしも音響に適しているわけではないし、場合によっては聖壇の横に控えて礼拝を進行を補佐したり、あるいは会衆への讃美を促すために後部の階上に席を設けるなどしました。オルガンについても同様な配置が考えられています。(トレント会議でのオルガン・ミサの扱いに注意) この時代はともかく凝った宗教曲が多い。19世紀のように寄せ集めの市民合唱団など目ではない。専門の聖歌隊が聖職者の地位にしっかり食いついていました。しかしいちど失われた聖職禄を礼拝堂のなかで再現するのは並大抵のことではありません。由緒あるほとんどの聖堂は数百年かけて接ぎ木のように増築されていますので、全体に良く響くものの、どの場所で歌うのが効果的か? 聖書朗読などナレーションに向いた位置はどこか? など、およそ一般のコンサート・ホールのように決まった法則というものがない。聖餐の盃を掲げる場所に適した場所が必ずしも音響に適しているわけではないし、場合によっては聖壇の横に控えて礼拝を進行を補佐したり、あるいは会衆への讃美を促すために後部の階上に席を設けるなどしました。オルガンについても同様な配置が考えられています。(トレント会議でのオルガン・ミサの扱いに注意) このように聖歌隊といっても、聖堂のデザインに従って、あるいは楽士の数などに合わせていくつかの楽器で代用することができたことからも、千差万別の解釈が成り立つわけで、要はそのシチュエーション全体のなかで作品の意図を理解することが肝心のようです。 これをオーディオ的にみるとどうかというと、個人的にはどんなに音の焦点がぼやけても無指向性マイクで録るのが好ましく感じられます。無指向性マイクでの収録は音の輪郭が曖昧なようでいて、音の遠近感が正確に収録され、天上の高さなど聖堂のアコースティックに関する情報が自然に感じられます。中世のモノディーでは聖堂での複合的な響きの混ざり具合が楽譜に書かれた音符以上の意味を持つときがありますし、フランドル楽派のポリフォニーは聖堂の響きの性格(ロマネスクか?ゴシックか?)が作品のテンポ感やアーティキュレーションの凹凸の与え方と不可分に思えます。これをマルチマイクとミキサーで人為的にバランスを取った録音では意味が薄められます。これは18世紀の構成の大きなオラトリオでも同様で、マイクに向かって漫才よろしくイエスとピラトが会話してるというのはあまりぞっとしません。やはり聖堂に漂うひんやりとした間を感じ取れるとき、初めて対話(ロゴス)の距離感と祈り(オラトリー)の客観性が保たれるように思うのです。 聖堂の残響は通常のオーディオ理論には備わっていないものがあります。ひとつは暗騒音で非常に低い周波数のゴーという音が常時鳴っています。広い聖堂ほど暗騒音は深く柔らかい。暗騒音はCDになってから収録されるようになったもので、LPではカートリッジのトラッキングを乱れさせる要因としてカットされていました。なので昔のQの高いウーハーでこの領域を再生すると共振してブルブル震えるようなときがあります。もうひとつは高域のアンビエンス領域での共鳴で、通常のホールに比べ高域成分が多く含まれています。高域での反射波はツイーターのキャラクターが乗りやすい領域で、素直に繋がるタイプでないとエコーが浮き上がったり、リンギングを起こしてポリフォニーの綾を掻き消してしまいます。装置全体の位相特性に一段と厳しい要求がされるわけです。 一時期2wayのスピーカーを使ってた頃は楽音とは別の付帯音が強調され、旋律の細かい音程が聞き取れないときがあったのですが、今は富士通テンのフルレンジに変えてかなりはっきりと音程が判るようになりました。フルレンジはトータルなハーモニクスのバランスが整っているので、古楽特有の旋法の違いを理解するときに非常に役立ちます。ワンポイント録音に対しシングルコーンでの再生はシンプルで無垢な音響を提供してくれると思います。 ページ最初へ 【夜の静寂に想いよせて】  バロックには華麗な格闘の世界があるとすれば、反対にメランコリックで静謐な世界がある。あえていえば暗鬱なパッションを秘めた楽器たちです。楽士の間でトンボゥ(墓碑)というエールを密かに捧げ合うフランスの流儀には恐れ入ります。これとは反対にイギリスのコンソートは賑やかな家族の団欒を楽しむような感じです。チェンバロはどうも好きになれないようで、あれで睡眠を求めたゴルドベルク伯の気持ちが理解できない。ベットで踊ってしまうのが趣味だったのかと皮肉のひとつでも云いたくなる。私はリュートやバス・ヴィオールのメランコリックな世界が好きです。 バロックには華麗な格闘の世界があるとすれば、反対にメランコリックで静謐な世界がある。あえていえば暗鬱なパッションを秘めた楽器たちです。楽士の間でトンボゥ(墓碑)というエールを密かに捧げ合うフランスの流儀には恐れ入ります。これとは反対にイギリスのコンソートは賑やかな家族の団欒を楽しむような感じです。チェンバロはどうも好きになれないようで、あれで睡眠を求めたゴルドベルク伯の気持ちが理解できない。ベットで踊ってしまうのが趣味だったのかと皮肉のひとつでも云いたくなる。私はリュートやバス・ヴィオールのメランコリックな世界が好きです。さりとてフランスの器楽曲が瞑想的な曲とは一慨にいえません。むしろジーグ、メヌエット、ガヴォットとダンスがそこかしこに散りばめてあります。あるいは社交の手間を省いたプライベートな時間を楽士と楽しむ趣味があったのか。王自身がリュートを練習していたという記録もあります。こうして貴族社会特有の社交辞令を盛り立てる音楽もあれば、プライベートに密やかに楽しむ音楽もある。夜の静寂(しじま)を豊かに満たす音楽と楽士のもてなし。これで一日の疲れを癒すというのは贅沢な望みというものです。 ガンバにしろリュートにしろ16c〜18cのオリジナル楽器はくぐもった音がします。単純にはガット弦は締め上げる力がモダン楽器に比べて弱いのと、弓の張力をより繊細に調整しながら弾く要素とが重なりあっています。このときの各弦に掛かる微妙な圧力の違いでメロディの綾が紡がれます。この暗褐色で占められる陰影に深みがないと、レンブラントの絵画のように対象が浮び上がってこない。デカルトは人間機械論のなかで、「身体の働きかけを受ける精神の受動passion が情念 passion であり、情念のメカニズムは体内の動物精気の動きによって生理学的に説明される」というように言っていますが、巧みな楽士ほど暗い色合いのなかでコントロールされたパッションを展開する技に長けているようです。 もうひとつの要素は和楽器でいうサワリのように、ピリオド楽器にも心地よいノイズがあります。それは楽譜にはないが奏法のうえで生じるもので、演奏者によってその扱いも異なります。私個人はこの手のサワリがピリオド楽器のエキゾチックな部分や演奏家の情熱的な表現に繋がると思ってるので、むしろ表現のひとつとして適度にコントロールされるべき要素のように思います。このサワリの部分はパーカッションのように過度特性が激しく、リンギングと位相が整理されたスピーカーでないと特定の周波数帯が目立ってしまい読んで字のごとく耳障りになりますが、逆に過度特性を抑え込み過ぎると詰まらない音になってしまう。この辺の真の緊張関係を保つのが難しいといえましょう。 ページ最初へ 【三人の音楽博士の訪問】 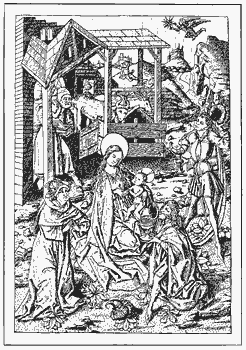 キリスト生誕の3人の賢者をもじっているのですが、ピリオド楽器奏者には博学な人が多い。初期は音楽学者が自身の理論を証明するために自ら楽器を手にしていた部分があり、そのため楽器とその演奏法を陳列したカタログ的色彩を帯びたものも少なくなかったのです。音楽史という言葉は今も残っているが、そうした文献学的興味を生き生きしたものとして再生する目的もあったようです。しかしバロック音楽は実は楽士の競争が激しかった時代で、自分のテリトリーのなかで自前の音楽を思い思いに提供していた時代でした。楽譜として残るのはそうした気運のなかの珠玉の作品であるという認識もあって当然です。 キリスト生誕の3人の賢者をもじっているのですが、ピリオド楽器奏者には博学な人が多い。初期は音楽学者が自身の理論を証明するために自ら楽器を手にしていた部分があり、そのため楽器とその演奏法を陳列したカタログ的色彩を帯びたものも少なくなかったのです。音楽史という言葉は今も残っているが、そうした文献学的興味を生き生きしたものとして再生する目的もあったようです。しかしバロック音楽は実は楽士の競争が激しかった時代で、自分のテリトリーのなかで自前の音楽を思い思いに提供していた時代でした。楽譜として残るのはそうした気運のなかの珠玉の作品であるという認識もあって当然です。一方で通奏低音のように明確な演奏法の指示がなくとも、当時の音楽家たちの慣習的な作法を読みとって楽譜を用意しなければならないものもあります。こうして考えるとバロック音楽の楽譜は料理のレシピのようなものであり、それを演奏する楽士はシェフのようなものです。ピリオド楽器の奏者に独立心の強い一種の誇りを感じる点は、こうした日々の楽譜と楽器の間に介在するパッションを、明確にカタチにしていく作業に裏打ちされているからのように思われます。それだけにシェフひとりひとりの手癖を楽しむような対話的な聴き方も、また楽しい日々です。楽器の音がこれだけ演奏する人の腕次第で味わいの変わるジャンルというのも珍しいからです。 3人の賢者といえば、独奏楽器と通奏低音によるトリオ・ソナタまたは組曲です。各楽器に卓越した名人が通奏低音の舞台のうえで踊りを披露する。当時はその花道を飾るのが作曲家自身だったことも多かったらしく、非常に技巧を凝らした作品の集中するジャンルでもあります。そんな類のソリチュードが目玉である一方で、厳格な様式感の支えは通奏低音のヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロに委ねられ、伴奏とはいってもコンチェルトのように互いのメチエが激しく対比するときもあり、いわば小さなオーケストラのような表情の多彩さが要求されるパートでもあります。独奏パートがひとつの楽器の技法に精通した名人とすれば、通奏低音はあらゆる音楽様式に精通した名士というべきだと思います。そのふたつの要素がどこまでも周回軌道を巡っていくとき、時間を忘れてしまうひとときが訪れるのです。 ページ最初へ 【ゴルドベルク氏は眠れない?】  ゴルドベルク変奏曲を聴いていつも思う。眠れない夜にこれを聴きだしたら朝までウキウキして眠れないのではないだろうか? そうピアノはおろかチェンバロでの演奏はコンサート向きでいたって賑やか過ぎるのです。最近になって息子のC.Ph.E.バッハのクラヴィコードのためのソナタをCDで聴く機会がありましたが、これこそ夜のしじまに合った安らぎの音ではないかと思います。クラヴィコードはまさにキーボード・サイズの卓上楽器で、訊けばプライヴェート・ルームでの室内楽器として18世紀にとても流行ったらしく、バッハも長男の教育用に作曲した他、いくつかの鍵盤楽器用組曲はクラヴィコードでの演奏が考えられています。そして次男のC.Ph.E.バッハは素人の御婦人が家庭での手習いで演奏できるピースを嫌々ながら書いてたと云っていますが、、その多感様式ともいわれる理知的で霊感的なスタイルから、18世紀のドイツ古典派の擁立に多大な影響を与えました。ハイドンも作風の確立期にC.Ph.E.バッハのクラヴィコード・ソナタを研究したといい、クラヴィコードを机代わりに作曲の筆を走らせる肖像画も残っています。そういう経歴も含めて室内で無理なく古典派の粋を楽しめるのがクラヴィコードなのです。 ゴルドベルク変奏曲を聴いていつも思う。眠れない夜にこれを聴きだしたら朝までウキウキして眠れないのではないだろうか? そうピアノはおろかチェンバロでの演奏はコンサート向きでいたって賑やか過ぎるのです。最近になって息子のC.Ph.E.バッハのクラヴィコードのためのソナタをCDで聴く機会がありましたが、これこそ夜のしじまに合った安らぎの音ではないかと思います。クラヴィコードはまさにキーボード・サイズの卓上楽器で、訊けばプライヴェート・ルームでの室内楽器として18世紀にとても流行ったらしく、バッハも長男の教育用に作曲した他、いくつかの鍵盤楽器用組曲はクラヴィコードでの演奏が考えられています。そして次男のC.Ph.E.バッハは素人の御婦人が家庭での手習いで演奏できるピースを嫌々ながら書いてたと云っていますが、、その多感様式ともいわれる理知的で霊感的なスタイルから、18世紀のドイツ古典派の擁立に多大な影響を与えました。ハイドンも作風の確立期にC.Ph.E.バッハのクラヴィコード・ソナタを研究したといい、クラヴィコードを机代わりに作曲の筆を走らせる肖像画も残っています。そういう経歴も含めて室内で無理なく古典派の粋を楽しめるのがクラヴィコードなのです。この楽器はフランドルやスペインで15世紀頃には使われはじめ、その後イタリア、フランスを経由してドイツにも波及したらしい。機構が簡単なだけあって、打鍵後の鍵盤の高さを動かすことで微妙に音程が動く。最初聴いたときはおもちゃのピアノのような稚拙さを感じたのですが、独特の歌うようなアーティキュレーションに気付いて以来、CDは店頭で見つけるごとに購入しています。歌うように感じる原因は強弱以外にも、即興的に調律の具合をコントロールできることで、一見機械的にも思える単純なアルペッジオの響きがいつでも必然的に聞こえ、古典派の作品において血の通った様式美に出会える希有な時間を過ごすことができます。この手作りの暖かい音楽にもてなされたら気持ちよく寝られること必須でしょう。 ページ最初へ |